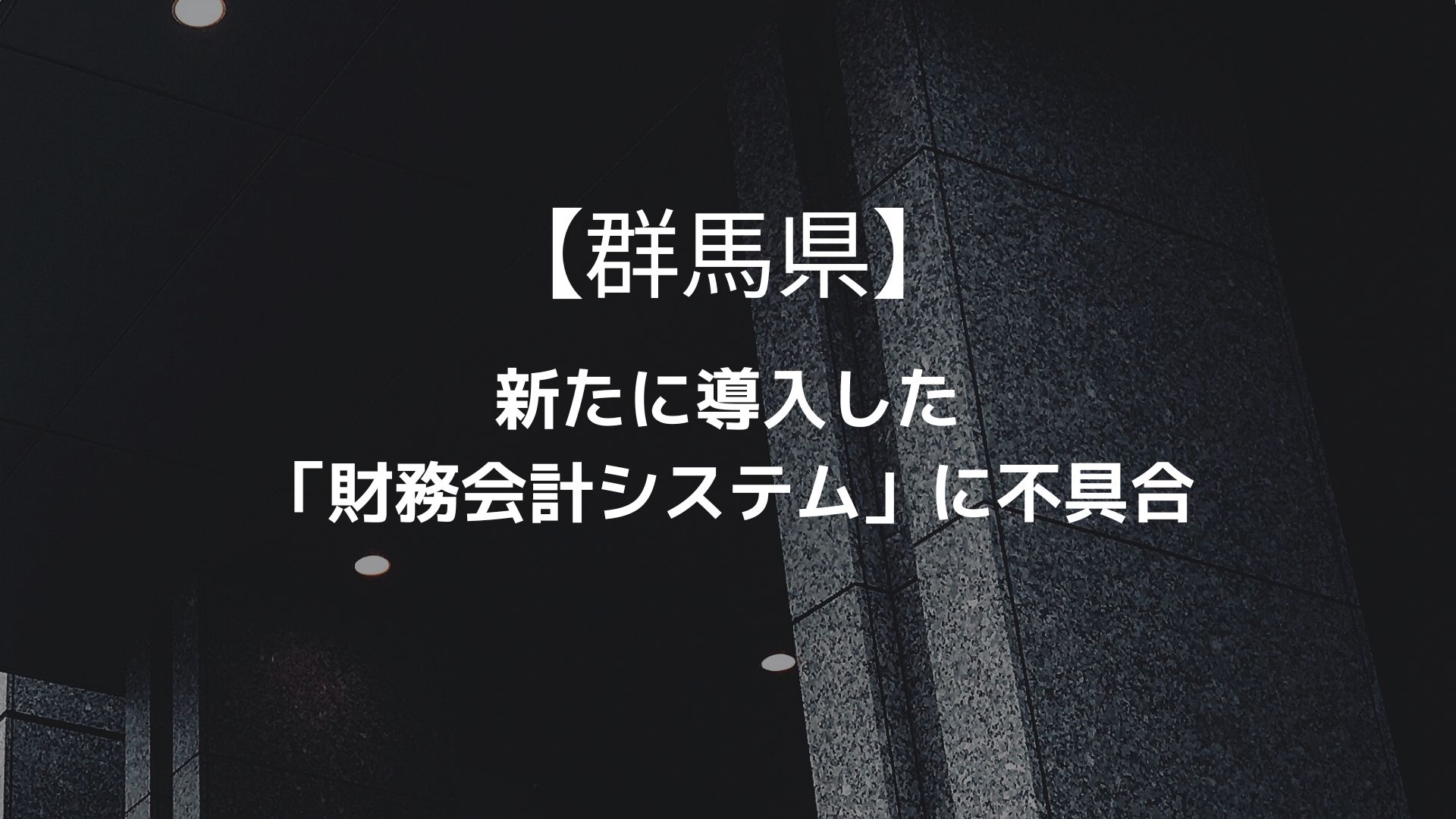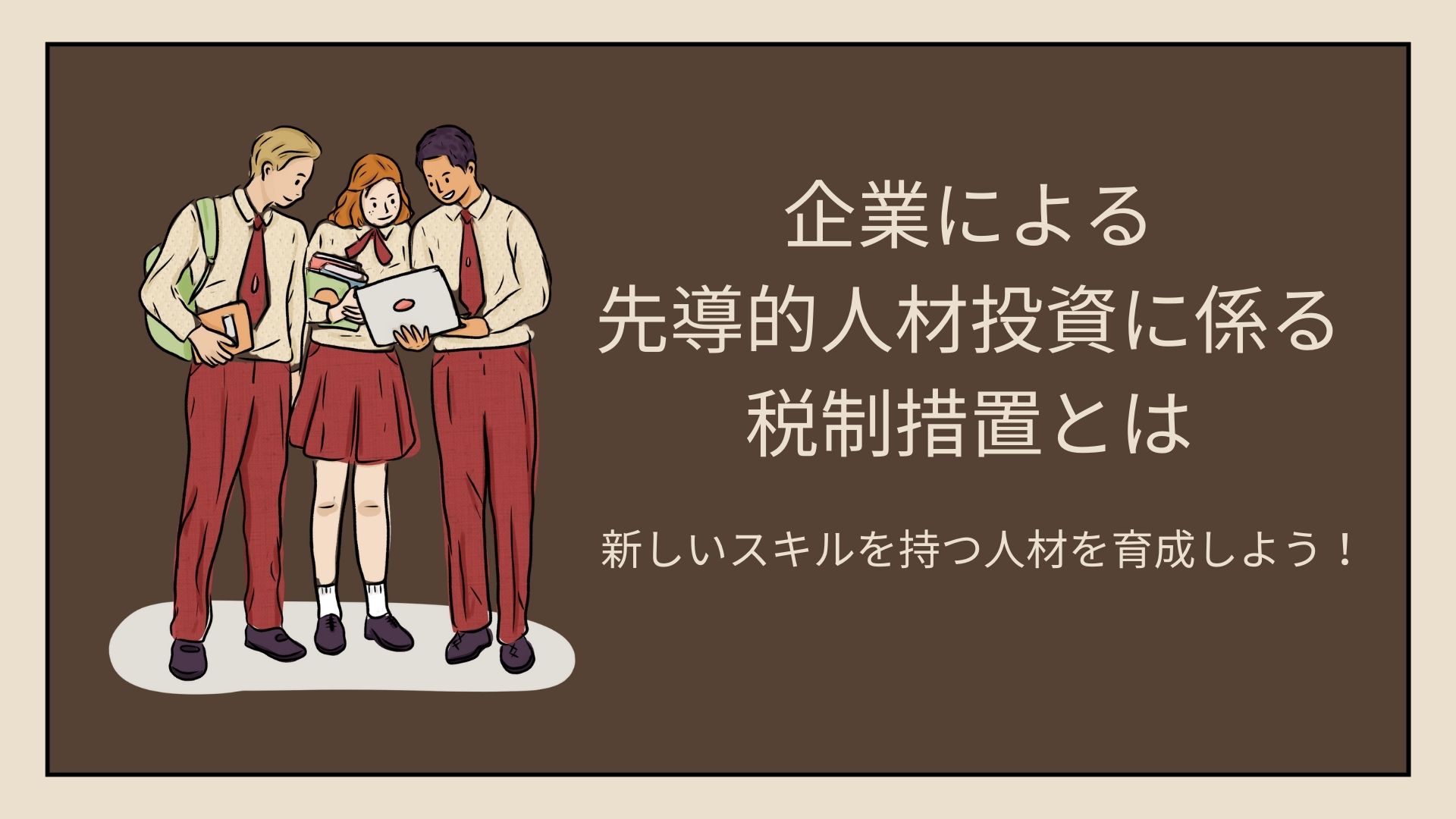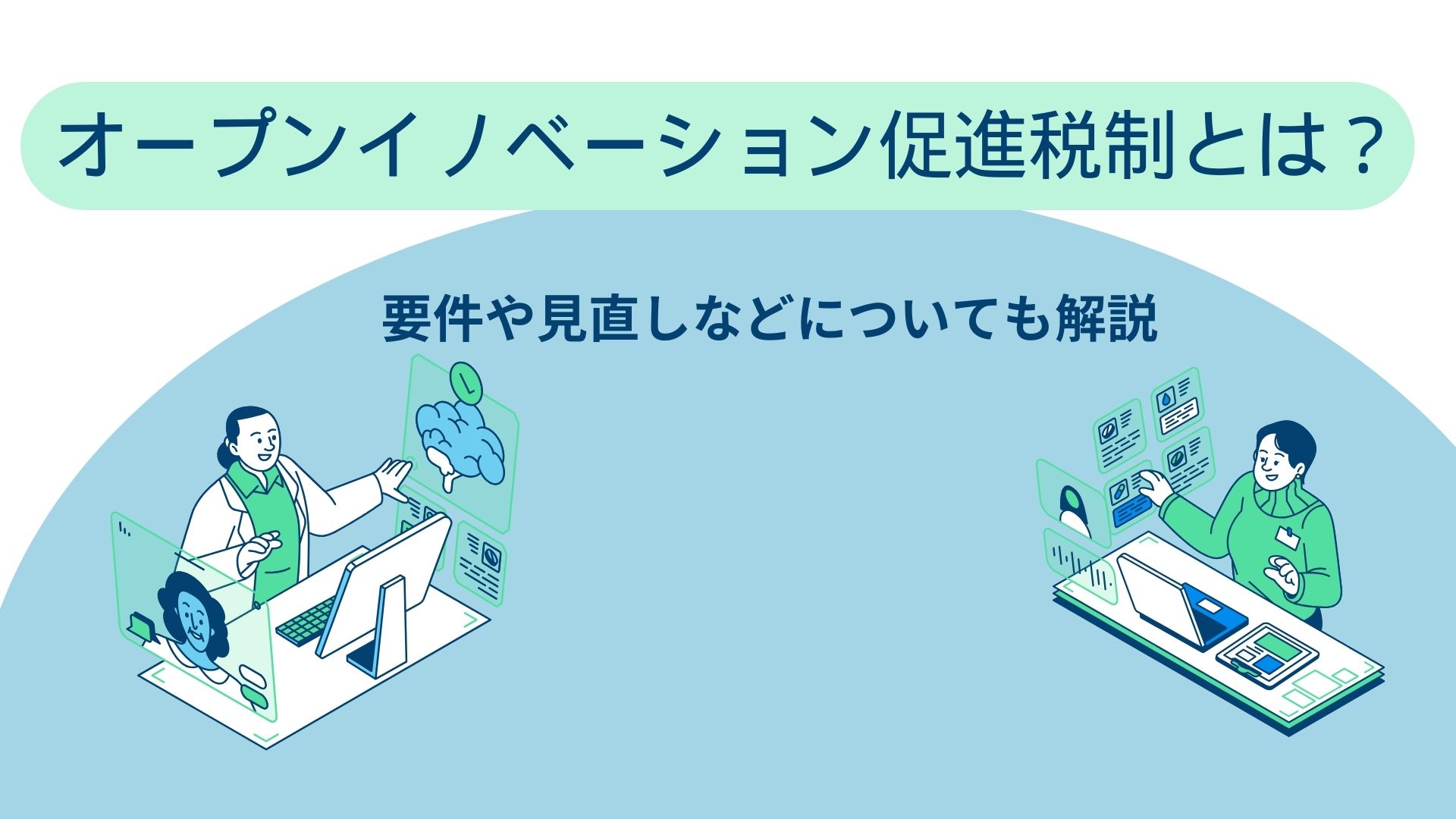お店や企業から領収書を受け取る際、「印鑑が押されていないけど大丈夫かな?」と不安に感じたことはありませんか?
また逆に、自分で領収書を発行する立場の方は、「印鑑は必ず押さないといけないの?」と迷うこともあるかもしれません。
結論から言うと、領収書に印鑑が押されていなくても、法的な効力は失われません。しかし領収書に記載しなければならない項目もあります。
今回は領収書における「印鑑」の役割などを解説します。
領収書とは、代金を受け取った事実を証明する書類。
領収書に印鑑が押されていなくても、法的な効力は失われません。
つまり、領収書に印鑑は必須ではありません。
領収書が有効なものとして認められるには、以下の5つの項目が記載されていることが重要です。
- 宛名(支払者の名称)
- 発行年月日
- 金額
- 何に対する支払いか(但し書き)
- 発行者(領収書を発行した会社の名称や住所など)
これらの要件が満たされていれば、税務調査などでも正式な証憑書類として認められます。

領収書に印鑑は必須ではないではないにも関わらず、なぜ多くの企業や店舗が領収書に印鑑を押しているのでしょうか?
それは、「発行元が確かにその会社である」ことを証明するため、つまり書類の信頼性を高めるための商慣習(慣例)です。
印鑑があることで、書類が偽造されたものではないという安心感を与え、経理処理をスムーズにする目的で用いられています。
偽造防止のためにも、領収書の印鑑はあったほうが良いでしょう。
必須ではない印鑑ですが、大企業や公共事業では「印鑑必須」としている場合があるため、注意が必要です。
取引先に失礼と思われないためにも、印鑑を押しておくのが無難です
領収書に印鑑を押す場合は、発行者の名称付近に「認印」を押すのが一般的。
社名ゴム印と併用して押すケースも多く、位置は、会社名や住所の文字の上に少しかぶるように押すのが慣例です。
訂正や二重線がある場合は、その箇所にも訂正印を押すと信頼性が高まります。
領収書に印鑑を押す際のポイントは以下の通り。
- 誰の印鑑を押すか:領収書を発行する個人事業主や法人の印鑑
- 法人:社名が入った角印(法人の認印)を使用するのが一般的
- 個人事業主:屋号印や個人名印を使用
- 押す位置:発行者(会社名や住所)の文字の上にかぶるように押すのが慣例
これらのポイントを押さえることで、より信頼性の高い領収書を発行・管理することができます。
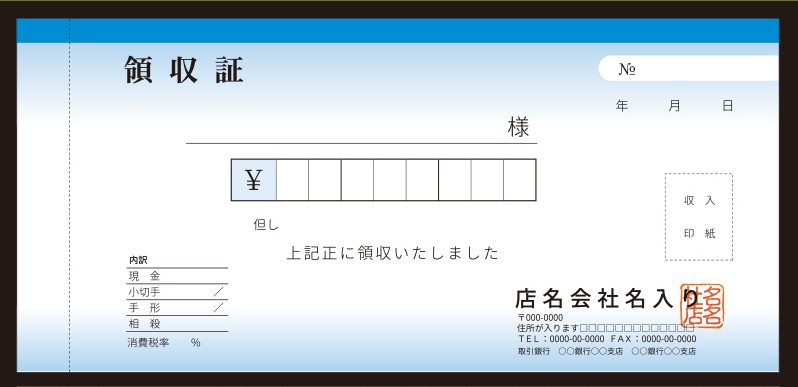
ここまで説明したとおり、領収書に印鑑は必須ではありません。つまり印鑑がなくても経費にできます。
税法上、経費計上に必要なのは「取引の事実を証明できる書類」であり、宛名・日付・金額・内容が記載されていればOK。
取引先や社内規定によっては印鑑を求められるケースもあるため、実務上は確認しておくと安心です。
ここで注意すべきなのが、「印鑑」と「収入印紙」を混同しないこと。
印鑑は、領収書の発行元を示すためのものであり任意です。
一方で、収入印紙は、契約書や領収書などに貼る、税金(印紙税)の証票であり、金額によっては必須です。
税法上、5万円以上の取引で発行する領収書には、原則として「収入印紙」を貼ることが発行者の義務となっています。
これは印紙税法で定められたルールです。収入印紙を貼っていないと、発行した側に過怠税が課される可能性があります。
この「収入印紙」は、貼った上で消印(割印)を押さなければなりません。そのため、「領収書にはハンコが必要」という認識が広まった一因とも言われています。

Q1. 領収書に印鑑は必要?
A1. いいえ。印鑑がなくても領収書として有効
Q2. 印鑑がない領収書は経費にできる?
A2. はい。宛名・日付・金額・内容・発行者の情報が記載されていればOK
Q3. 領収書に印鑑を押す理由は?
A3. 書類の信頼性を高めるため
Q4. 領収書の印鑑はどこに押す?
A4. 発行者の名称付近に押すのが一般的
領収書に印鑑は法律上必須ではありません。
しかし信用性や取引慣行の観点から、印鑑を押すのが一般的。
もし印鑑がなくても基本的には有効ですが、経理処理や取引先対応で不便が生じる可能性があるため、印鑑がある方が望ましいでしょう。
発行側としては印鑑を押す習慣を持ち、受け取る側としては印鑑がない場合に備えて、発行者の記載や内容を確認しておくと安心です。
DFEブログでは、今後もこのような今更聞けない素朴な疑問などを発信してまいりますので、どうぞお楽しみに!