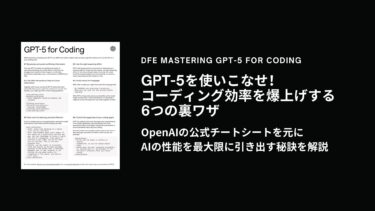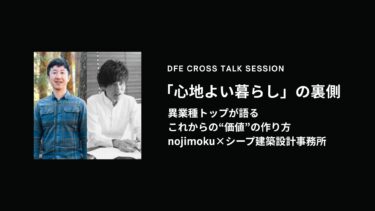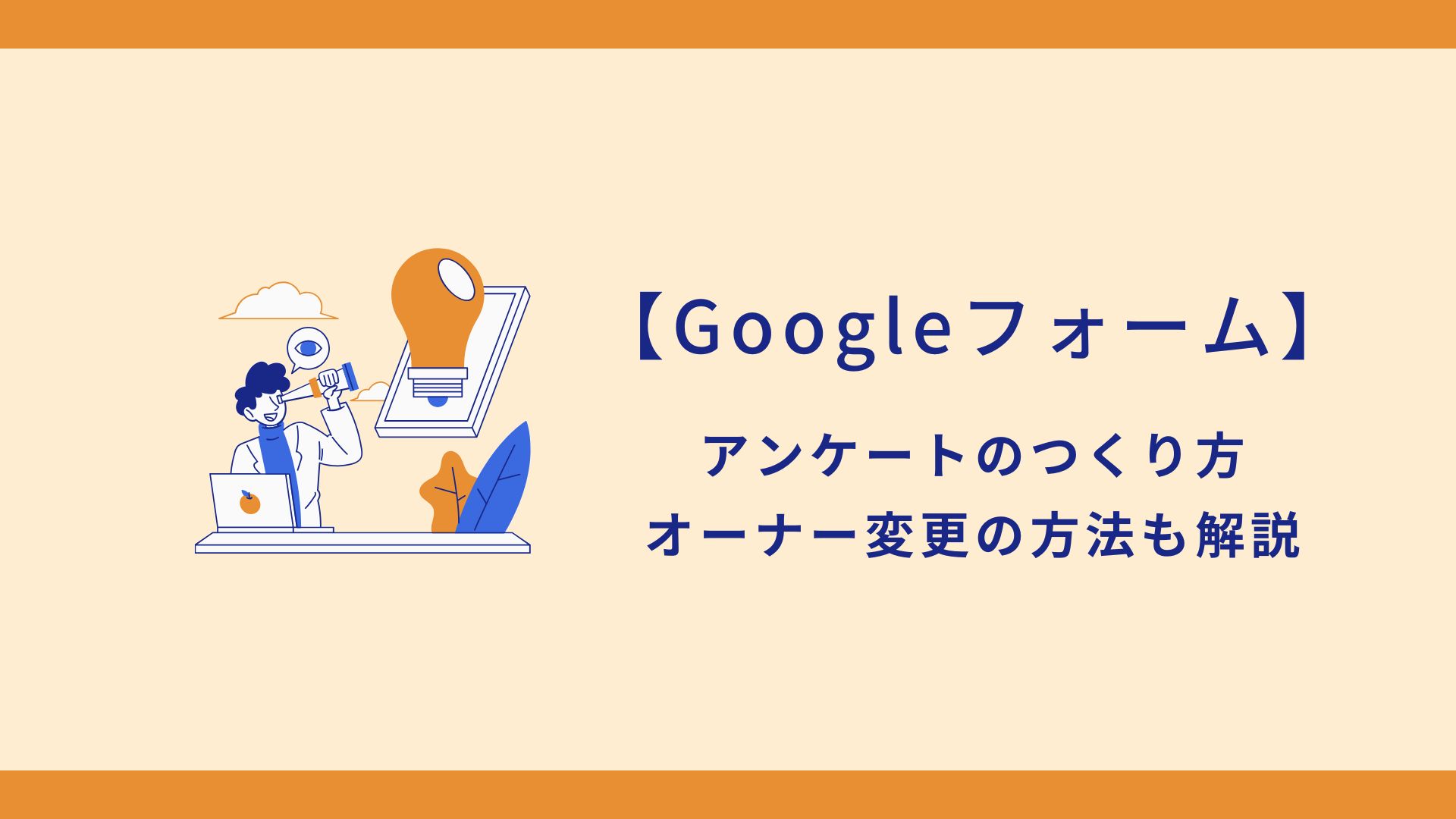これまでの検索エンジンは、「キーワード」を入力して情報を探すものでした。
しかし近年はChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し、ユーザーはAIと対話や質問をしながら、答えを直接AIから導き出すようになりました。
これまでは、検索で上位表示されるために「SEO(検索エンジン最適化)」を意識していましたが、今、状況は大きく変わろうとしています。
これまでの常識だったSEOだけでは通用しない時代となり、新たな概念「GEO(生成エンジン最適化)」が重要視され始めているのです。
今回は、「SEO時代の終焉」と「AI時代の新常識」について、GEOの視点から解説します。
SEO(Search Engine Optimization)は「Google検索で上位表示されるための最適化手法」。キーワード選定や被リンク対策、テクニカルSEOなどがその中心でした。
こういった施策を行い、検索順位を高めることによって、企業の成果を大きく左右してきました。
しかし現在は、検索そのものが変化しています。
生成AIがWeb上の情報を要約して直接回答する「ゼロクリック検索」が主流になり、ユーザーはWebサイトを訪れずとも答えを得られるようになりました。
つまり、検索結果で上位に表示されることの価値が相対的に低下し、従来のSEO戦略だけでは、集客が難しくなると考えられます。SEO市場は確実に変わりつつあるのです。

検索のルールが変わるなかで、新しい基準で選ばれるための考え方がGEOです。
GEO(Generative Engine Optimization)とは、生成AIの回答に自社のコンテンツを「引用・参照」してもらうための施策です。
ユーザーがAIに質問を投げかけた際、信頼性の高い情報源として自社のコンテンツが選ばれ、回答の根拠として提示されることを目指します。
これにより、たとえ直接サイトへのアクセスがなくても、ブランドや情報に触れる機会を創出することができるのです。
つまり「SEO」が検索結果の順位で上位にいく施策であるのに対し、「GEO」はAIが生成する「答え」に自社の情報を含ませること。
従来のSEOと、これから重要になるGEOは似ているようで大きく異なります。まずは両者の違いを整理してみましょう。
| 項目 | SEO(検索エンジン最適化) | GEO(生成エンジン最適化) |
| 目的 | 検索結果ページで上位表示を狙う | AIが生成する回答に引用・採用される |
| 対象 | GoogleやBingなどの検索エンジン | ChatGPT、Claude、Perplexityなど生成AI |
| 施策の中心 | キーワード対策、内部施策、外部リンク | 構造化された情報提供、Q&A形式、エビデンス提示 |
| 評価基準 | 検索順位・クリック数 | AIが回答に取り上げる頻度・内容の信頼性 |
| 重視する要素 | 被リンク数、コンテンツ量 | 信頼性(出典)、独自性(一次情報)、明確さ |
| ブランド露出 | 検索結果にリンクとして表示 | AIの回答文中に「○○社」と記載される |

では、具体的にGEOではどのような対策が求められるのでしょうか。紹介します。
- 情報を整理し、AIに理解されやすい形にする
- ユーザーの質問に直接答える記事づくり
- 信頼性を示すエビデンスを盛り込む
- 独自性のある一次情報を発信する
- ブランド名を明確に織り込み、認知を高める
AIは文章全体を丸暗記するのではなく、「意味のまとまり」を分解して学習・回答に使います。
そのため、人間にとって読みやすいだけでなく、AIにとっても抽出しやすい形に整えることが重要です。
具体的には、見出しタグ(H2/H3)、箇条書き、表、Q&A形式を積極的に活用しましょう。
「◯◯とは何か?」をH2に設定し、その直下に簡潔な定義を置く。これだけでAIが“回答用テキスト”として拾いやすくなります。
生成AI検索は、従来の「キーワード検索」ではなく「自然な質問文」を前提にしています。
「△△のやり方は?」「〇〇のメリットは?」といった疑問をそのまま入力するユーザーが増えているのです。
したがって、記事内では想定される質問を見出し化し、その直後に端的な答えを置くのが効果的。
さらに、回答の後に「補足解説」や「事例紹介」を続けると、人間読者にもAIにも価値あるコンテンツとなります。
生成AIは「正確さ」と「信頼性」を強く意識して回答を組み立てます。
そのため、単なる主張だけでなく、データ・統計・公式の調査結果を積極的に引用することが不可欠です。
引用元をURL付きで明示すれば、AIが「この情報は裏付けがある」と判断し、回答に採用される確率が上がります。
また、外部データを示すことで読者からの信頼も獲得でき、二重の効果を期待できます。
AIは膨大な既存情報を参照していますが、似たような二次情報ばかりだと埋もれてしまいます。
そこで重要になるのが、独自の調査データ・顧客インタビュー・自社のノウハウといった一次情報です。
例えば「自社顧客100名へのアンケート結果」や「社内での成功事例」などは、他にはない唯一の情報源となり、AIから高く評価されやすくなります。
結果として、「AIにとって唯一無二の引用元」として選ばれる可能性が高まります。
GEOでは「どのサイトが答えを出すか」よりも「誰の情報が引用されるか」が重要です。
そのため、記事内には自然にブランド名・サービス名・企業名を散りばめましょう。
AIが回答を生成する際に「○○社の調査によると…」と記載してくれることで、リンクがなくてもブランド露出が実現します。
これはSEOにはなかった新しいブランディング効果であり、GEO対策の大きな魅力のひとつです。
Q. GEOとは?
A. 生成AIの回答に、自社のコンテンツを引用や参照してもらうための施策
Q. SEOとの違いは?
A. SEOは検索順位を上げる施策、GEOはAIの回答に選ばれるための施策
Q. 具体的に何をすればいい?
A. 情報を整理し、質問に答え、エビデンスや独自情報を示し、ブランド名を盛り込む
Q. GEO対策のメリットは?
A. サイト訪問がなくてもブランド露出や認知拡大につながる
Q. 今すぐ始めるべき?
A. はい。AI検索は急速に普及しており、早く着手した企業が優位に立てる
これからの検索は、順位争いではなく“AIの答えに選ばれる”ための戦いに変わります。
SEOからGEOへ。今から準備を進めることが、AI時代のマーケティング成功のカギとなるでしょう。
DFEブログでは今後もビジネスシーンで役立つ情報を発信していきます。