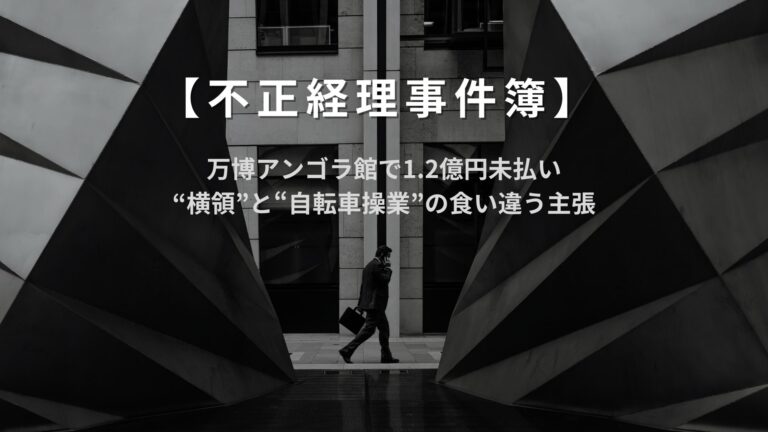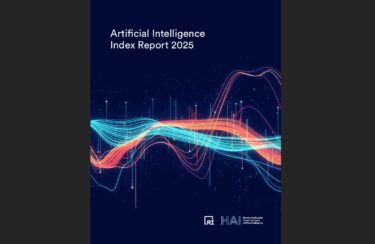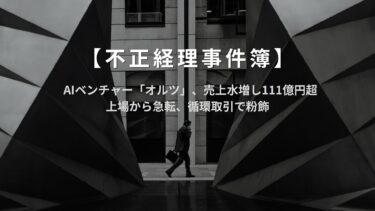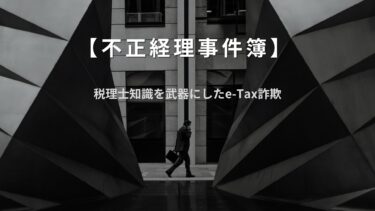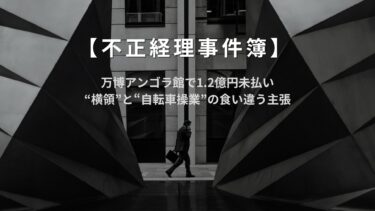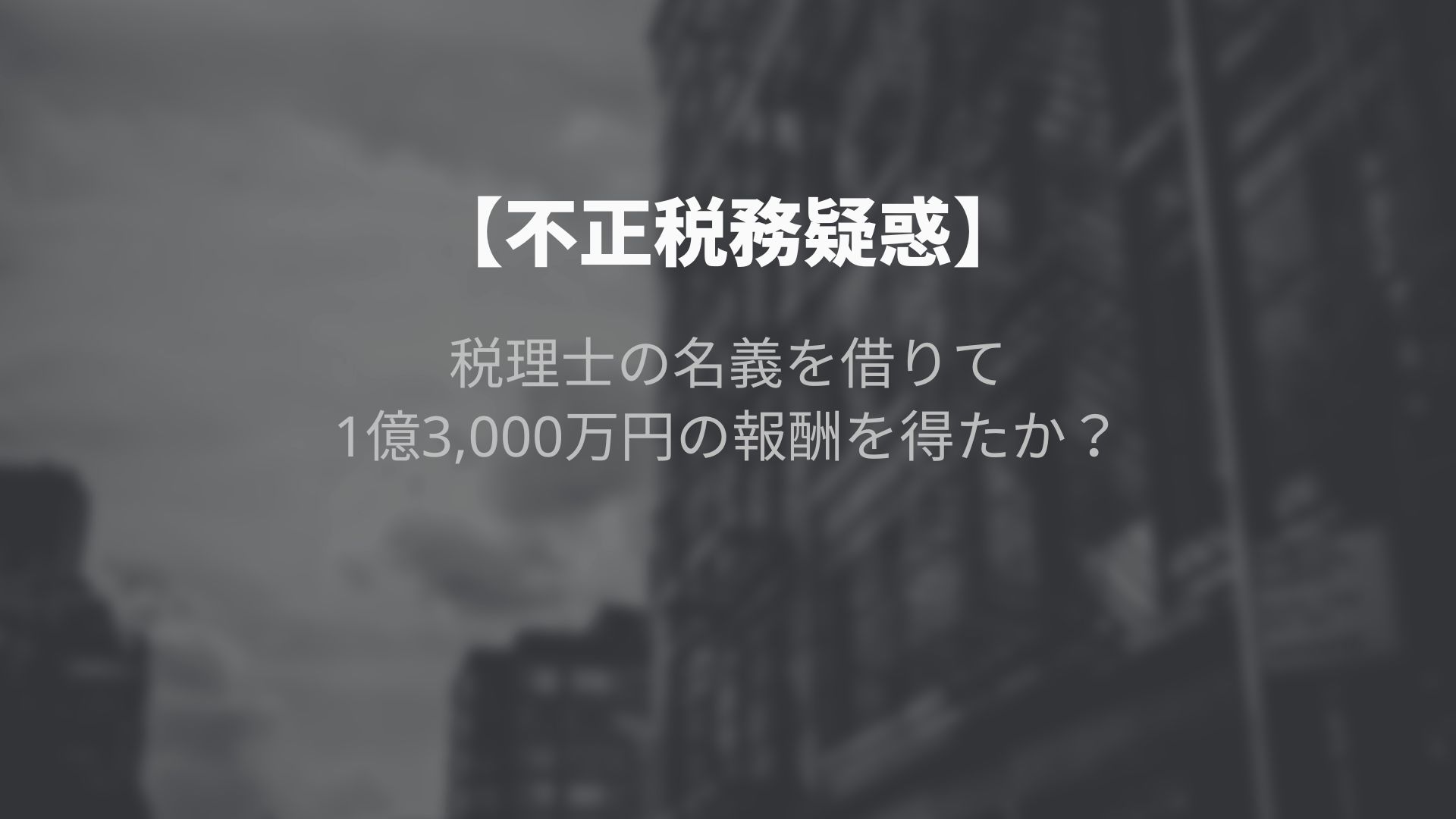巨額の横領や未払い問題が報じられるたびに、「自分の会社では起きない」と思っていませんか?しかし不正はいつも静かに進行します。どんな会社でも、気づかぬ落とし穴があるかもしれません。
今回紹介するのは、現在開催中の大阪・関西万博で起きた巨額の資金トラブル。
「アンゴラパビリオン」の工事費未払い問題が、関係者間の刑事告訴へと発展し、泥沼の様相を呈しています。国家プロジェクトであっても、こういった不正事件は起こり得るのです。
今回は、この不正事件について取り上げます。
騒動の中心にいるのは、大阪市鶴見区に本社を置く建設会社「一六八(いろは)建設」。
2025年大阪・関西万博のアンゴラ共和国パビリオンの工事をめぐるトラブルを抱える企業として、注目を集めています。
同社が抱える問題は、大きく分けて2つ。順に紹介します。

事の発端は、一六八建設がアンゴラパビリオンの内装工事を請け負う中で、下請け業者5社に対し、総額1億円を超える工事費の支払いが滞ったことでした。
その理由について、同社の社長は「経理担当者が会社口座から約1億2000万円を着服したため、支払いができなくなった」と説明し、7月28日、業務上横領の疑いで経理担当者の男性を刑事告訴。
告訴状によれば、男性は2023年11月から2024年5月にかけ、26回にわたり会社の口座から約1億2000万円を着服した疑いが持たれています。
これに対し、告訴された経理担当者は「前の工事で支払えていなかった分を補填しただけで、私的に使ったお金は一切ありません」と主張。横領を否定しています。
また「もともと一六八建設には自転車操業的な資金繰りがあり、自分が貸し付けていたお金を回収しただけ」とも語っています。
さらに一六八建設は、建設業法で定められた許可を得ずに、万博工事を請け負っていたことも判明。
大阪府から30日間の営業停止処分を受けています。
この点についても社長は「経理担当者に申請を任せていたが、結果的に提出されていなかった」と主張。
一方、経理担当者は「建築士との関係が悪化し、申請ができなかった」と説明しており、社長側が全ての責任を押し付けている構図に対し、真っ向から反論しています。
このように両者の言い分は完全に食い違っており、社内のガバナンスが完全に崩壊していた実態がうかがえます。

今回の問題は、一企業の不祥事にとどまらず、万博という公的事業における構造的な課題を浮き彫りにしています。
アンゴラ館の工事は、発注元であるNOE JAPANから吉拓、大鵬を経て一六八建設へと仕事が流れる多重下請け構造になっていました。
公金が投入される大規模事業特有の「多重下請け構造による中抜き」や「監督責任の空洞化」が、今回の問題の温床になったとの指摘もあります。
こうした構造の根本的な見直しが求められるのではないでしょうか。
いずれの主張が真実であったとしても、最終的に甚大な被害を被っているのは、汗水流して工事に従事した下請け業者であることに変わりはありません。厳格な検証が求められています。
Q1:どんな問題が起きたのか?
万博アンゴラ館の工事で、建設会社が下請け業者に約1億円を支払わなかったことが発覚
Q2:原因は?
会社は「経理担当が1.2億円を横領した」と主張。一方、経理担当は「資金繰りの穴埋めをしただけ」と反論
Q3:なぜここまで混乱したのか?
未払いだけでなく、建設業許可の未取得や多重下請け構造により、責任の所在が曖昧になっていたため
「経理担当者が悪い」「建築士と連携が取れなかった」と、責任のなすり合いでは、根本的な解決には至りません。万博のような国家的イベントにおいて、こうした構造的なリスクが現実化したことは、軽視できない問題です。
今回の事件は、ガバナンスの不全、契約構造の不透明さ、監督体制の欠如といった、公的事業の脆弱さを浮き彫りにする事案。
「もし自社で同じことが起きたら」と想像してみてください。
内部不正や業務の属人化は、規模や業種に関係なく、どんな企業にも起こりうるリスクです。
だからこそ、経理業務のアウトソーシングという選択肢を、今一度真剣に検討してみてはいかがでしょうか。第三者によるチェック体制を設けることで、ガバナンスの強化と不正の抑止につながります。
経理アウトソーシングは、DFEにお任せください。