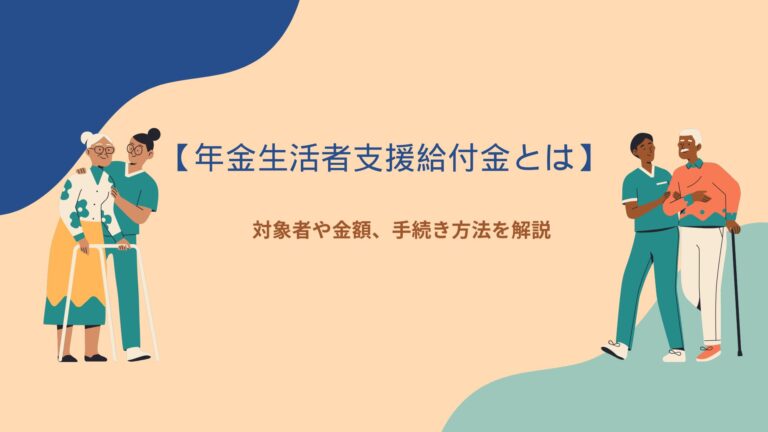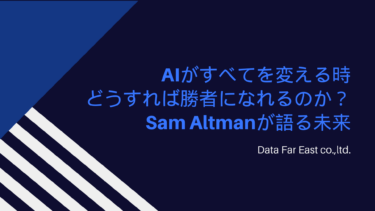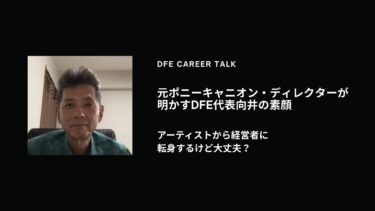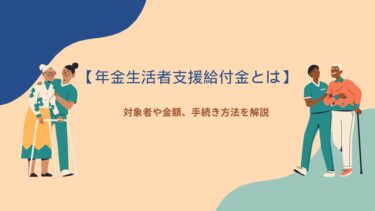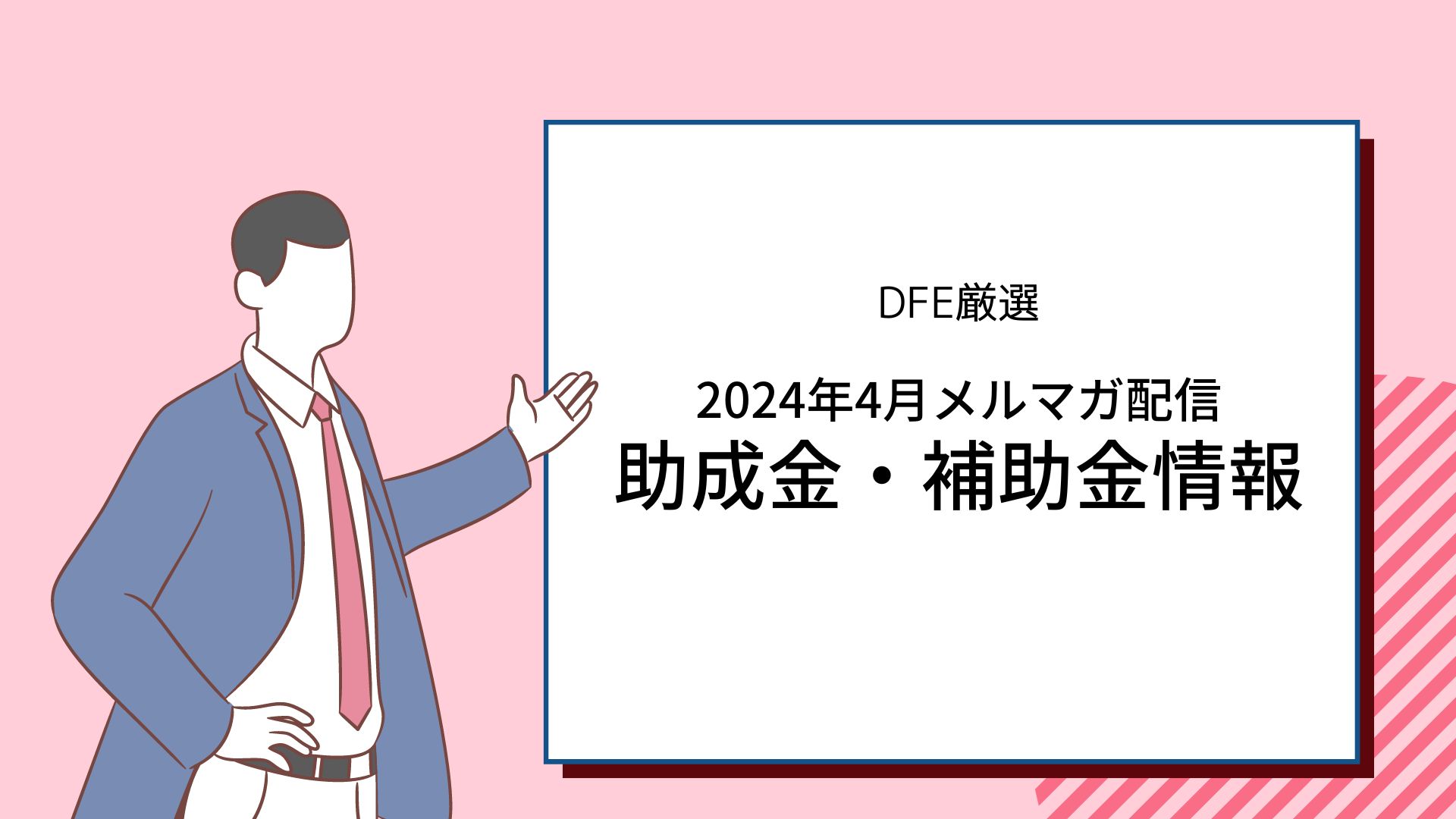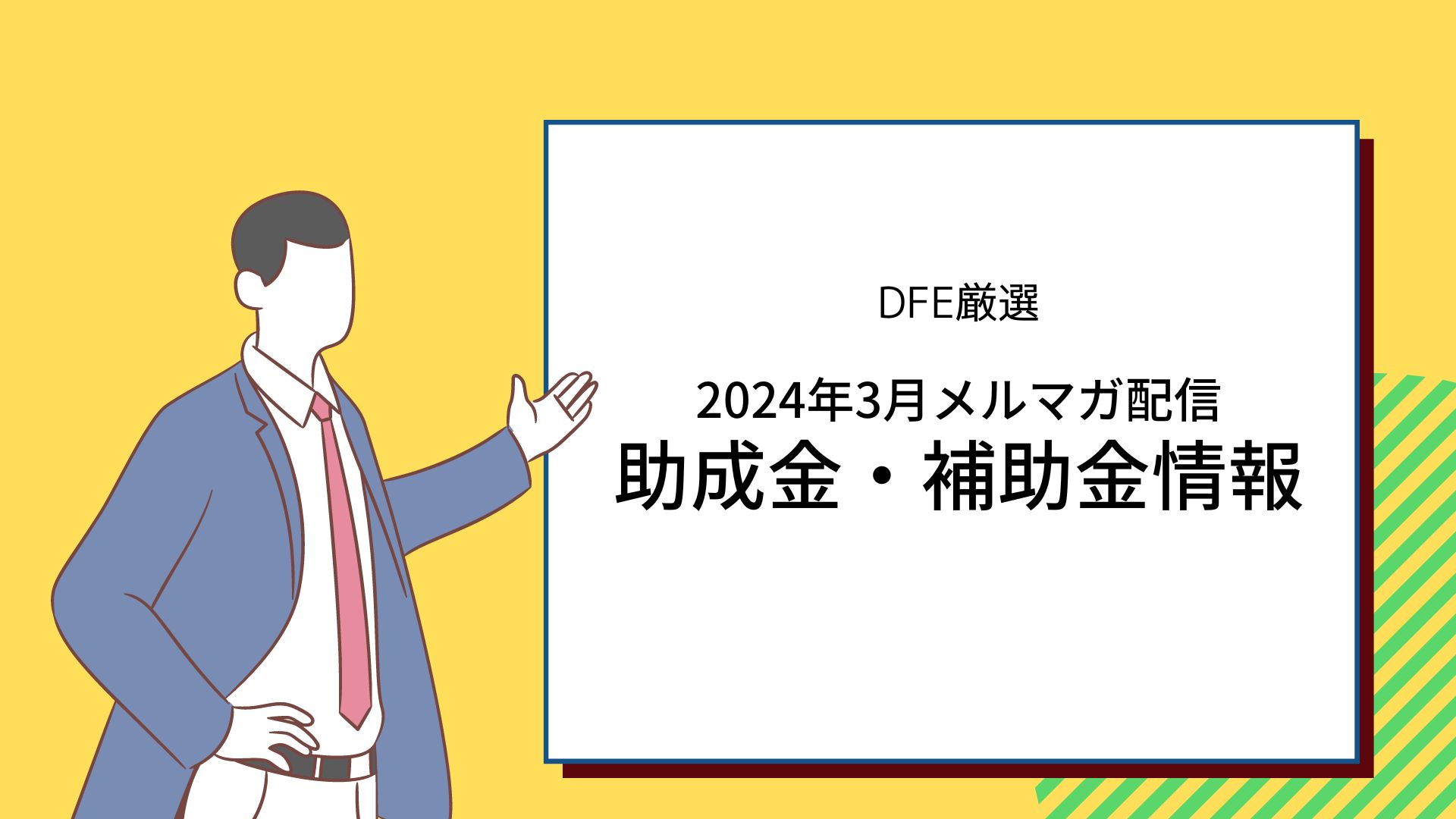日本は超高齢社会を迎え、多くの高齢者が年金を頼りに生活しています。
しかし、年金額が少ない方や生活が厳しい方にとっては、年金だけでは十分な暮らしを維持するのが難しいのが現実です。
こうした状況を踏まえて、2019年10月から始まったのが「年金生活者支援給付金制度」。
これは、所得が一定以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される国の制度です。
今回は、年金生活者支援給付金の制度について解説します。
年金生活者支援給付金の支給要件(対象となる方)は以下のとおりです。
以下3つすべての要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が889,300円以下であること
※障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この所得には含まれません。
昭和31年4月1日以前に生まれた方は887,700円以下となります。
以下2つの要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が4,721,000円 + (扶養親族の数 × 38万円) 以下であること
※障害年金などの非課税収入は、この所得には含まれません。
以下2つの要件を満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が4,721,000円 + (扶養親族の数 × 38万円) 以下であること
※遺族年金などの非課税収入は、この所得には含まれません。

給付金額は一律ではなく、年金額や所得水準によって変わります。
老齢基礎年金受給者は、月5,020円(満額の場合)、年金額が少ない方は段階的に減額。障害・遺族基礎年金受給者は、月5,020円です。
年間で考えると、6万円前後の支援を受けられます。
給付額は、(1)保険料納付済期間に基づく額と(2)保険料免除期間に基づく額の合計となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
5,450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
約11,551円×保険料免除期間/被保険者月数480月
障害等級によって、月額が決まっています。
障害等級2級:月額 5,450円
障害等級1級:月額 6,813円(2級の1.25倍)
月額 5,450円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。

給付金を受け取るためには、原則として請求手続きが必要です。
老齢・障害・遺族基礎年金の裁定請求手続きとあわせて、年金事務所または市区町村の窓口で請求手続きを行ってください。
新たに支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内(緑色の封筒に入ったはがき型の請求書)が毎年9月頃から順次送付されます。
届いた請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函するだけで手続きは完了です。請求した月の翌月分から支給が開始されます。
一度認定請求を行い、受給が決定すれば、翌年以降の請求手続きは原則不要
請求手続きが遅れると、受け取れる給付金の総額が減ってしまう可能性があります。ご案内が届いたら速やかに手続きを行いましょう。
Q1. 対象者は?
A1. 老齢・障害・遺族基礎年金の受給者で、所得や住民税が一定以下の方
Q2. 自動的にもらえる?
A2. いいえ。自分で請求手続きを行う必要あり
Q3. 給付額は?
A3. 基準は月額5,450円。老齢年金は納付期間や所得で増減、障害年金は等級に応じて、遺族年金は原則5,450円
年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない方々の生活を支える大切な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、案内が届いた際には忘れずに手続きを行いましょう。
不明な点があれば、お近くの年金事務所や年金生活者支援給付金専用ダイヤル: 0570-05-4092(ナビダイヤル)に問い合わせることをお勧めします。
DFEブログでは、今後もさまざまなビジネス情報のほか、助成金や補助金の情報を発信していきます。