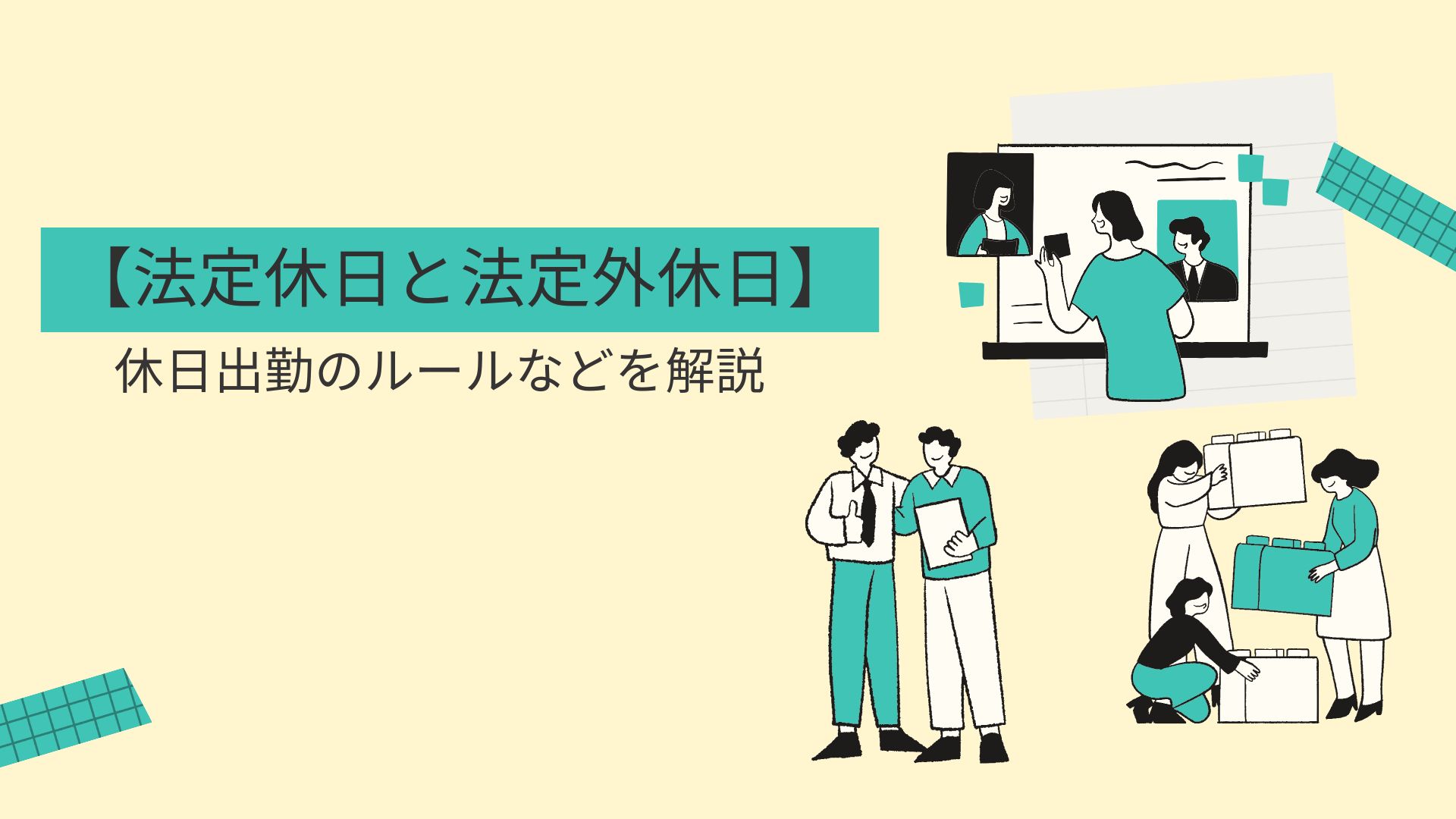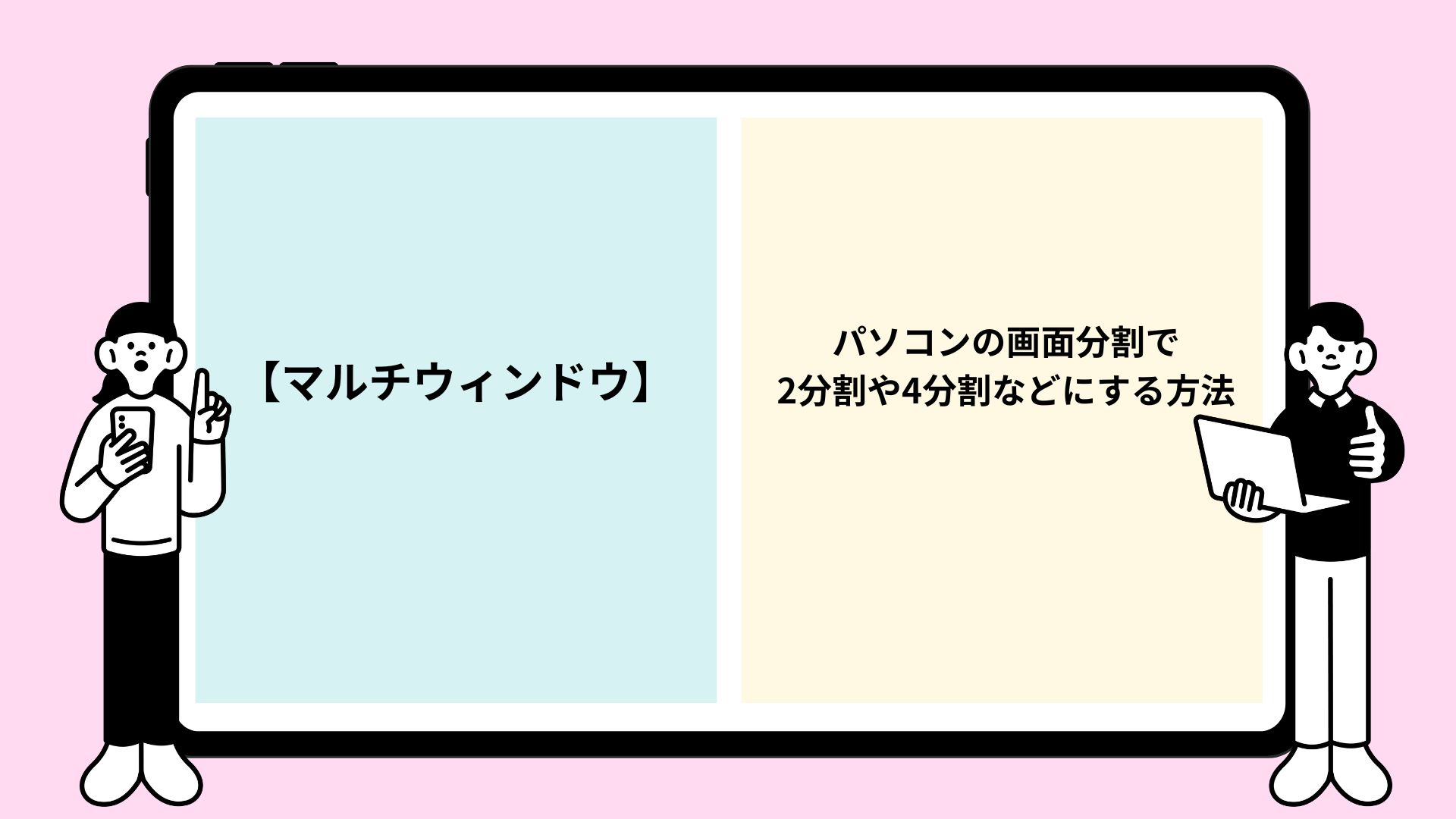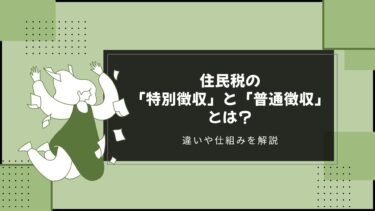「忙しくて休みが取れない…」そんな言葉をよく耳にします。
しかし日本の企業は、従業員に対し、1週間に少なくとも1回(または4週間で4日以上)の休日を付与することが義務づけられています。これが法定休日です。
一方で、法定休日に加えて企業が独自に設定する休日が法定外休日。
今回は、法定休日と法定外休日の違いや休日出勤の注意点を解説していきます。
労働基準法第35条に基づき、週1日または4週間で4日以上の休日を設定する義務があります。この休日を法定休日と呼び、企業は必ず設定しなければなりません。
法定休日を労働者に与えなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
法定休日に加えて企業が独自に設定する休日のことです。
例えば、週休2日制の企業の場合、1日は法定休日、もう1日は法定外休日に該当します。
労働基準法では、企業がどの曜日を休日とするかについて、具体的な指定はありません。
企業は、業務の都合に合わせて柔軟に休日を決めることができ、毎週異なる曜日を休日にすることも可能です。
法的義務はありませんが、労働環境の安定や休日出勤時の対応を明確にするためにも、就業規則で休日を特定しておくことが望ましいとされています。
休日を明示することで、従業員の働きやすさ向上や賃金計算の混乱防止にもつながるでしょう。
休日を明確に定めていない場合は、週の起算日を把握することが重要です。
一般的に、日本では日曜日を週の起算日とする考えが広く用いられているので、例えば、土日休みの企業で法定休日が明確でない場合、週の最後の休日(通常は日曜日)が法定休日となるのが一般的です。
どちらか一方のみ勤務した場合は、労働しなかった方を法定休日として扱います。

労働基準法では、休日労働や時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が規定されています。
- 法定休日に働いた場合:通常賃金の35%以上
- 法定外休日に働いた場合:時間外労働扱いにならない限り割増賃金は不要
- 時間外労働(1日8時間・週40時間超)に該当する場合:通常賃金の25%以上
- 深夜労働(午後10時から午前5時まで)に該当する場合:通常賃金の25%以上
- 時間外労働かつ深夜労働の割増賃金に該当する場合:通常賃金の50%以上(時間外25%+深夜25%)
法定休日と法定外休日で、企業が注意すべきポイントは主に次の4つ。
- 就業規則で休日の定義を明確にすること
- 割増賃金の計算ミスを防ぐこと
- 振替休日と代休の違いを理解すること
- 36協定を遵守すること
企業は就業規則で法定休日と法定外休日の違いを明確にし、社員に周知することが重要です。
振替休日は、事前に休日を別の日に移動すれば割増賃金不要です。一方代休は、休日労働後に休みを付与し、休日労働の割増賃金は支払い義務があります。
36協定(サブロク協定)とは、時間外労働や休日労働を行う際に、企業が労働組合または労働者代表と協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要がある制度のこと。
36協定がない場合は、法定休日労働を命じることは原則として違法となり、企業には罰則が科される可能性があります。
また法定休日に勤務させる場合、36協定があっても通常賃金の35%以上の割増賃金を支払うことは義務です。
法定休日と法定外休日の違いを理解し、適切な労務管理を行うことは、企業にとって重要な課題でしょう。
特に割増賃金のルールを正しく適用することは重要です。労働トラブルを防ぎ、従業員の適正な労働環境を確保するためにも、給与計算業務は業務委託が安心かつ安全です。給与計算ならDFEにお任せください。