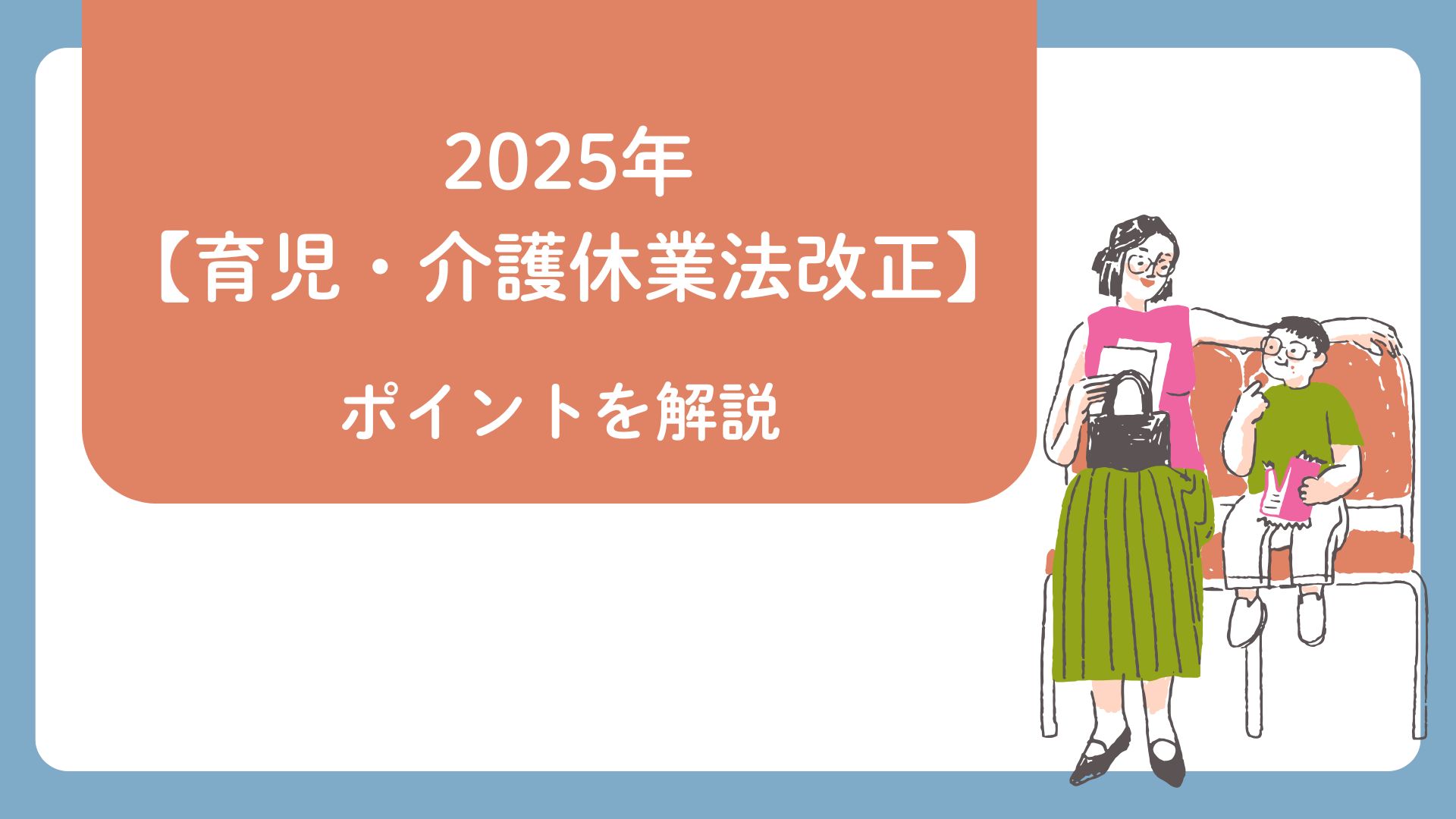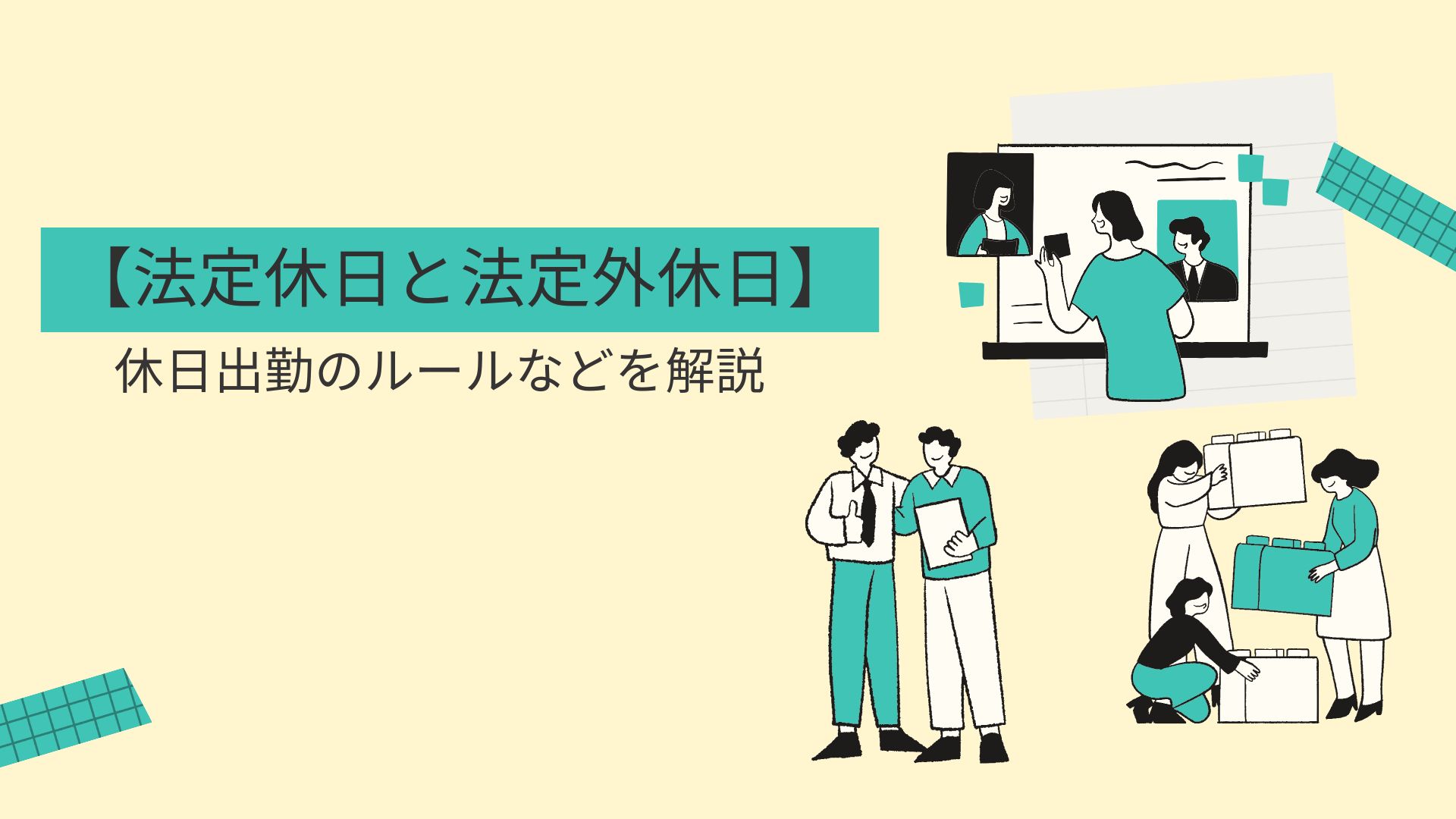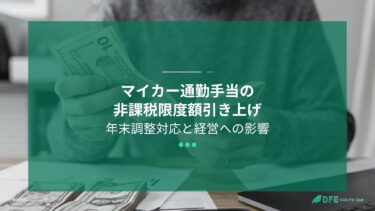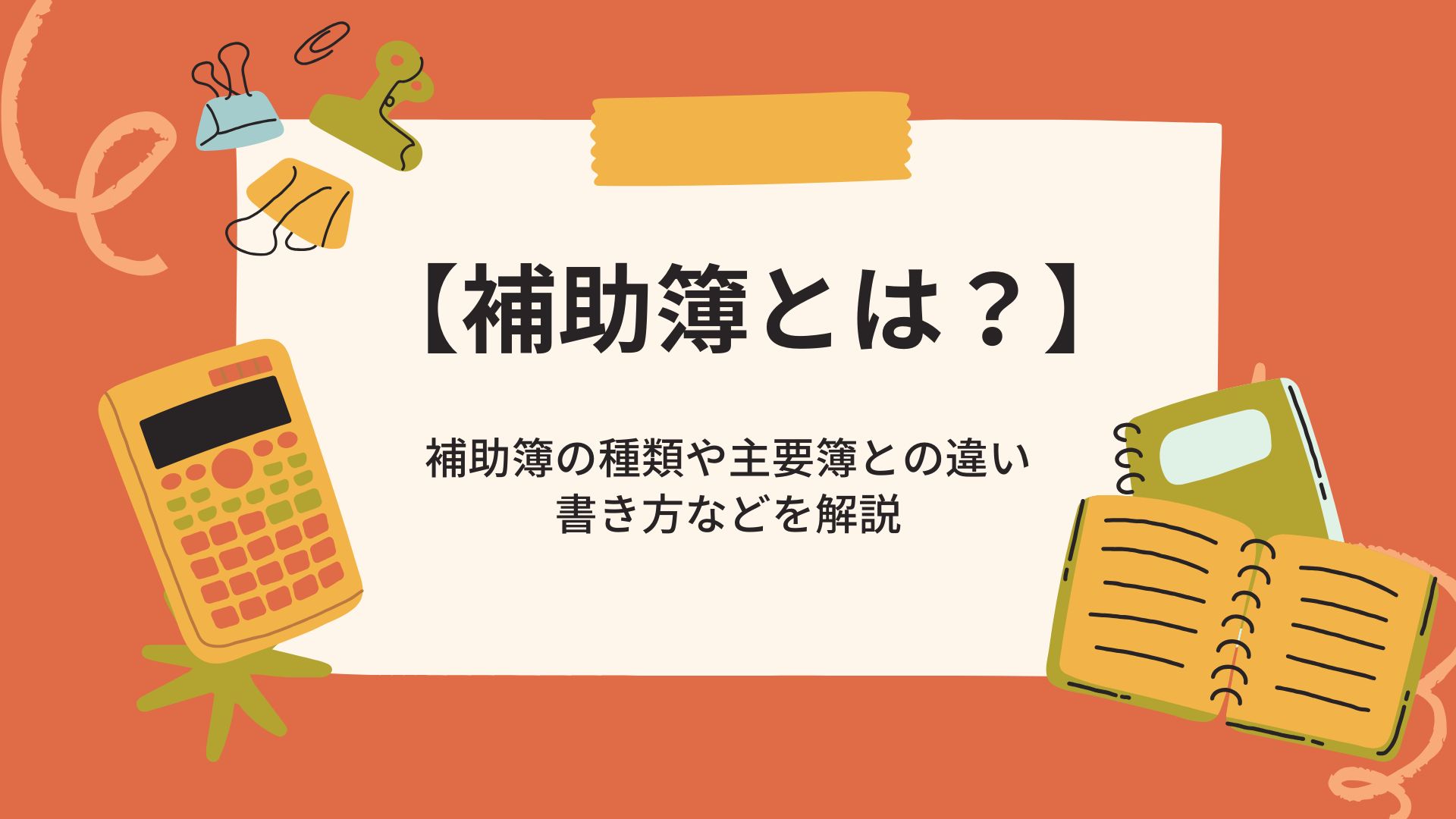インボイス制度を経てよく耳にするようになった、消費税の「免税事業者」と「課税事業者」という言葉。
個人事業主やフリーランスとして活動する方の中には、「免税事業者でも消費税を請求してよいのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論から言うと、免税事業者も消費税を請求することができます。免税事業者が消費税相当額を上乗せして請求した場合でも、その分を税務署に納付する義務はありません。
今回は、免税事業者の消費税の取り扱いについて解説します。
消費税法において、一定の条件を満たす事業者は消費税の納税義務を免除されることがあります。このような事業者を「免税事業者」と呼びます。免税事業者になる条件は以下のとおりです。
- 基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下
- 設立1期目および2期目の法人(資本金1,000万円未満の場合)
この条件を満たすと、事業者は消費税の申告・納付をしなくてもよくなります。
免税事業者(インボイス制度)について詳しくはコチラの記事をご覧ください。
免税事業者であっても、消費税を請求できます。
免税事業者は消費税の納税義務がありませんが、取引先に対して請求書上で消費税相当額を含めた金額を請求することは可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
免税事業者であることを明示せず、消費税を含んだ金額を請求すると、後にトラブルになる可能性があります。
取引先によっては、消費税相当額を支払わない方針の会社もあるので、注意してください。
2023年10月に開始されたインボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行できるのは課税事業者のみです。
免税事業者が発行した請求書では、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引を避けられる可能性があります。
免税事業者が消費税相当額を上乗せして請求した場合でも、その分を税務署に納付する義務はありません。
ただし請求時に「消費税」と明記すると、取引先から誤解を招く可能性があるため、「税込価格」として総額表示するのが一般的です。

インボイス制度の導入により、免税事業者は次の影響を受ける可能性があります。
仕入税額控除を利用できないため、取引先が課税事業者との取引を優先することが考えられます。
消費税分を上乗せしにくくなり、実質的な値引きを求められる可能性があります。
取引の継続や価格交渉のしやすさを考慮し、課税事業者への転換を検討する事業者も増えています。
免税事業者のままでいることが不利になるケースも増えています。自分のビジネスの状況を見極め、適切な選択をすることが重要です。
免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかは、以下の点を考慮して決めるとよいでしょう。
- 小規模な事業であり、取引先から消費税相当額を受け取らなくても影響が少ない
- 一般消費者向けのビジネスで、消費税分を価格に転嫁しやすい
- 取引先が法人で、インボイスを求められることが多い
- 仕入れや経費が多く、仕入税額控除のメリットを受けられる
免税事業者であっても、消費税相当額を請求することは可能です。消費税相当額を上乗せして請求した場合でも、その分を税務署に納付する義務もありません。消費税を上乗せして請求するかは個人の判断に委ねられます。
消費税を上乗せすれば、その分売り上げも上がるので、消費税相当額を請求するほうがメリットがあるといえます。
しかし取引先によっては、消費税相当額を支払わない方針の会社もあるので、注意してください。
免税事業者のままでいることが不利になるケースもあるので、適切な選択をすることが重要です。
経理に関するお困りごとは、DFEにお気軽にご相談ください。