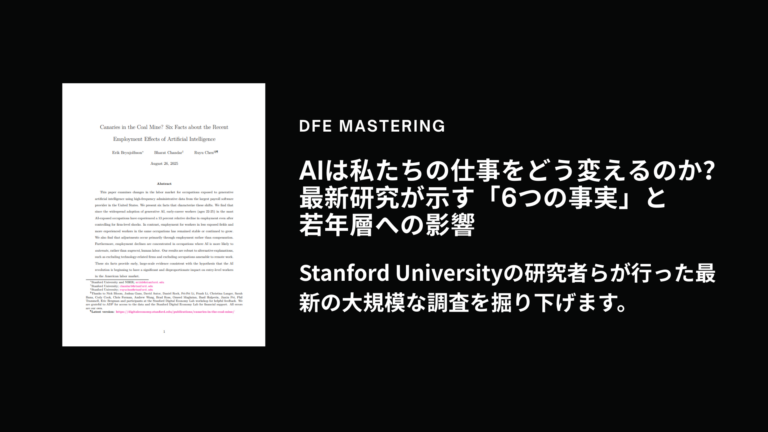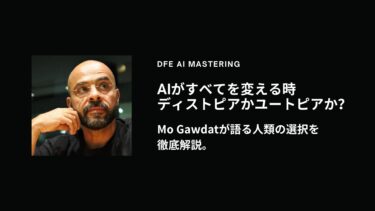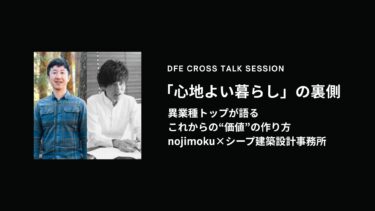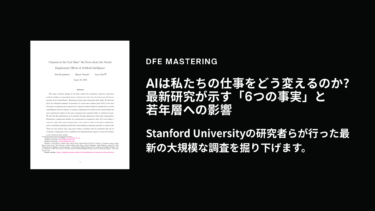今日の社会で最も注目されているテーマの一つが、生成AIが私たちの仕事や経済にどのような影響を与えるのかという点です。生成AIは驚くべき速さで社会に浸透しており、すでにアメリカ人の約40%が仕事や家庭で生成AIを利用していると報告されています。このような急速な普及を背景に「AIは私たちの仕事を奪うのか?」「それとも新たな機会をもたらすのか?」という疑問は、多くの人にとって非常に現実的な問いとなっています。
https://digitaleconomy.stanford.edu/wp-content/uploads/2025/08/Canaries_BrynjolfssonChandarChen.pdf
この重要な問いに答えるため、本記事ではStanford Universityの研究者らが行った最新の大規模な調査「Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence」に基づき、実際のAI利用データと大規模な雇用データから明らかになったAIと仕事のリアルな関係性について深く掘り下げて解説します。
この研究は、米国最大手の給与計算ソフトウェアプロバイダーであるADP社の高頻度な管理データを活用しています。このデータセットは、2025年7月までの月次個人レベルの給与記録を網羅しており、数百万人の労働者と数万社の企業にわたる膨大な情報を元にしています。これにより、AIの広範な普及以降の雇用動向を、高い粒度でリアルタイムに近い視点から追跡することが可能になりました。
本研究では、以下の方法でAIの影響度を測定しています:
- AI曝露度 (AI Exposure): Eloundou et al. (2024) によるGPT-4ベースの曝露度測定と、Anthropic社の生成AIモデルClaudeの利用データ (Handa et al., 2025) に基づく曝露度測定の2つのアプローチを使用しています。後者では、Claudeへのクエリがそのタスクを「自動化」するものか「拡張」するものかの区分も行っています。
- 職業の分類: 米国労働省のO*NETデータベースに定義された「仕事の活動(Work Activities)」を基に、SOCコード(Standard Occupational Classification code)を用いて職業を分類しています。
これまでのAIの影響予測が専門家やLLMの判断に基づいてきたものが多いのに対し、この研究は実際の雇用データに裏打ちされた、より実証的な知見を提供している点で大きな意義があります。
本研究では、AI革命が米国の労働力にどのような影響を与えているかを評価する6つの重要な事実を提示しています。
2.1. 若年層(22-25歳)のAI高曝露職種で雇用が大幅減少
最も重要な発見の一つは、AIに最も曝露度の高い職業、例えばソフトウェア開発者やカスタマーサービス担当者において、若年層(22-25歳)の雇用が大幅に減少しているという点です。具体的には、2022年後半から2025年7月にかけて、これらの若年層の雇用は最大で13%の相対的な減少を経験しています。
対照的に、同じ職種でもより経験豊富な労働者(35-49歳など)や、介護補助員(ヘルスエイド)のようなAI曝露度が低い職種では、雇用は安定しているか、引き続き増加していることが示されています。
2.2. 全体的な雇用は堅調も、若年層の雇用成長は停滞
米国全体の雇用は引き続き堅調に推移しており、パンデミック後の失業率は低いままですが、若年層の雇用成長は2022年後半以降停滞していることが示されています。
特に22~25歳の労働者については、AI曝露度の高い職種で2022年後半から2025年7月にかけて6%の雇用減少が見られる一方で、高齢の労働者では6~9%の増加が観察されています。この結果は、AI曝露度の高い職種における雇用の減少が、22~25歳の若年層全体の雇用成長の鈍化を牽引していることを示唆しています。
2.3. AIは「自動化」で雇用を減少させるが、「拡張」では変化は限定的
AIのすべての利用が雇用減少につながるわけではないことが明らかになりました。
- 自動化 (Automative): AIが人間の仕事を代替する用途(例: 指示に沿ったタスクの完全な委任、環境からのフィードバックに基づいたタスク完了)では、若年層の雇用が減少しています。
- 拡張 (Augmentative): AIが人間の能力を強化する用途(例: 協調的な改善プロセス、知識の習得、作業の検証と改善)では、雇用減少は見られず、むしろ雇用が増加している職種も確認されています。 この事実は、AIが労働を「代替」する場合には雇用を減少させるが、「補完」する場合にはそうではないという考えと一致しています。
2.4. 企業レベルのショックを考慮しても、若年層の雇用減少は変わらず
景気変動や金利上昇といった産業や企業レベルのショックが、AI曝露度の高い若年層の雇用減少パターンを説明する可能性も考えられます。しかし、本研究では企業-時間効果(firm-time effects)を制御する統計分析を行った結果、22-25歳の若年層においてAI曝露度の最も高い職種では、最も低い職種と比較して雇用が12ログポイント(約13%)減少していることが判明しました。
この結果は、観察された雇用トレンドが、AI曝露度の高い若年層を不均衡に雇用する企業への差動的なショックによって引き起こされているわけではないことを意味します。
2.5. 労働市場の調整は賃金よりも雇用に顕著
雇用動向とは対照的に、AI曝露度が賃金に与える影響は限定的でした。年齢やAI曝露度による年間基本給の傾向には、ほとんど差異が見られませんでした。これは、短期的には賃金に硬直性がある可能性を示唆しており、AIは少なくとも初期段階では賃金よりも雇用に大きな影響を与える可能性があることを示唆しています。
2.6. 様々な条件下でも結果は一貫
上記5つの事実は、様々な代替的なサンプル構成や頑健性チェックの下でも概ね一貫して見られました。
- テクノロジー職種の除外: コンピューター関連職種や情報セクターの企業を除外しても結果は類似していました。
- リモートワークの可否: リモートワーク可能な職種、そうでない職種のいずれにおいても、AI曝露度の高い若年層の雇用成長が鈍化する傾向が見られました。
- 長期的なサンプル: 2018年まで遡って分析しても、生成AIが普及した2022年後半(ChatGPTが2022年11月にリリースされた頃)以降に、AI曝露度と雇用の逆相関が顕著になることが確認されています。
- 学歴: 大卒者の割合が高い職業でも低い職業でも、同様の傾向が見られました。特に大卒者の割合が低い職種では、AI曝露による雇用動向の乖離が40歳までの幅広い年齢層で見られることが示唆されています。 これらの結果は、AIの影響が特定の職種や状況に限定されるものではなく、広範な労働市場に影響を与えていることを示しています。
AIがなぜ他の年齢層よりもAI曝露度の高い若年層に悪影響を与える可能性があるのでしょうか? 一つの可能性として、AIはモデルのトレーニングプロセスによって、形式知(codified knowledge)、つまり「教科書的知識」を代替しやすい性質があると考えられます。これは、正式な教育の中核をなす知識です。
一方で、AIは暗黙知(tacit knowledge)、すなわち経験によって蓄積される固有のコツやノウハウを代替しにくい傾向があります。若年層は経験豊富な労働者と比較して形式知をより多く提供するため、AI曝露度の高い職種でタスクの代替に直面しやすく、結果として雇用の再配分(減少)が大きくなる可能性があります。経験豊富な労働者は、蓄積された暗黙知によりAIによるタスク代替の影響を受けにくいと考えられます。
今回の調査はAIと仕事の未来を理解するための貴重な一歩ですが、いくつかの限界も存在します。
- 単一のAIプラットフォーム: 本研究は、ADPのデータと関連するAI曝露度測定に基づいており、米国の労働市場全体を完全に代表しているわけではありません。また、他のAIプラットフォームや利用状況を完全に反映しているわけではない可能性もあります。
- 仕事/レジャーの区別: AIとの会話が仕事の文脈で行われたものか、レジャー目的で行われたものかを正確に判断することは困難です。
- 影響の「大きさ」の判断: 会話データのみから、AIが仕事の活動に与える影響の「大きさ」を正確に判断することは困難です。
AIの急速な進化に伴い、職業がどのように再編成され、あるいは全く新しい職業が生まれるのかは今後の重要な研究課題です。今日の雇用の大半が、過去100年間に新しい技術の登場によって生まれた職業であることを考えると、AI時代にも同様の変化が起こる可能性は十分にあります。今後も継続的に雇用トレンドを追跡し、AIの能力の進展と私たちがそれをどのように活用し、社会の選択としていくかに注目していく必要があります。
この調査は生成AIが現在のところ、特に知識労働やコミュニケーション中心の職業の若年層に顕著な影響を与えていることを示しています。AIは情報収集、文章作成、コミュニケーションといった活動を「自動化」または「支援」することで、人間の生産性を高める可能性を秘めていますが、一方で若年層の雇用減少という課題も浮き彫りにしています。
しかしすべての職業が等しく影響を受けるわけではなく、身体労働や機械操作を伴う職業への影響は小さいか、ほとんどないことが示唆されています。
AIは私たちの仕事を「自動化」するだけでなく、多様な形で「拡張」し、新たな価値を創造する可能性を秘めています。AIとの共存は、私たちが自身のスキルや役割を再考し変化に適応していくことを求めるでしょう。AIの進化は止まることなく、私たちの仕事の未来は、AIの能力の進展と、私たちがそれをどのように活用し、社会の選択としていくかにかかっています。
Q1: この研究の主な目的は何ですか?
A1: この研究は、生成AIの広範な採用が労働市場に与える影響を、ADPの広範な雇用データを用いて特徴付けることを目的としています。特に、AI曝露度の高い職業における雇用の変化に焦点を当てています。
Q2: AIはどの年齢層の雇用に最も大きな影響を与えていますか?
A2: AI曝露度の高い職業では、22〜25歳の若年層が最も大きな影響を受けており、2022年後半以降、雇用が最大で13%相対的に減少しています。対照的に、同じ職種でも経験豊富な労働者や、AI曝露度が低い職種では雇用は安定または増加しています。
Q3: AIの「自動化」と「拡張」は雇用にどのように影響しますか?
A3: AIが仕事を「自動化」する用途(例: 指示に沿ったタスクの委任)では、若年層の雇用が減少する傾向にあります。一方、AIが人間の能力を「拡張」する用途(例: 協調的な改善プロセス)では、雇用への変化は限定的であり、むしろ増加している場合もあります。
Q4: 賃金への影響はありますか?
A4: 雇用とは対照的に、AI曝露度と年齢による年間基本給の傾向に大きな差異は見られませんでした。これは、短期的には賃金に硬直性がある可能性を示唆しています。
Q5: この研究の限界は何ですか?
A5: この研究は、単一の給与計算ソフトウェアプロバイダー(ADP)のデータに限定されており、米国の経済全体を完全に代表しているわけではない可能性があります。また、観測された事実が生成AI以外の要因によって影響されている可能性も指摘されています。
AIの導入は必須課題であるとともに、弊社の事務処理ということもAIを中心としたオペレーションにすべきという観点がより明確になりました。DFEでは、8割AIによる作業を目指して社内でのAI開発を進めています。ただお客様と接するコミュニケーションや納品物というラストワンマイルは人間にしたいという考えです。
自社でAI活用まで取り込めないという企業の方はぜひDFEにお声がけください。バックオフィスを完全アウトソーシングするだけでAI活用企業に生まれ変わることが可能です。
お問い合わせは下記より AIによる効率化などもお手伝い可能なDFEにバックオフィスをお任せください。