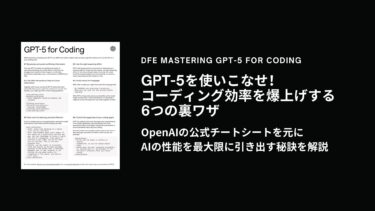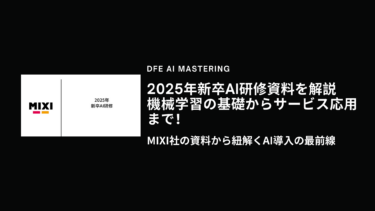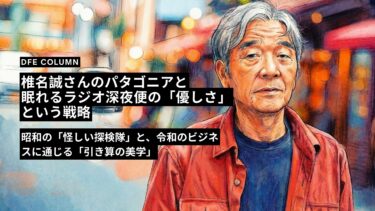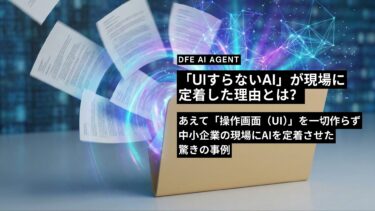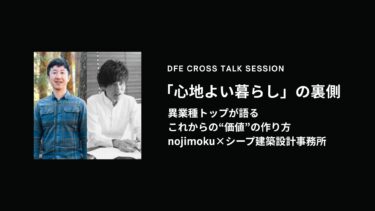2022年11月、世界は生成AIの産声を聞いた。ChatGPTの登場からわずか3年弱。その進化は我々の想像を絶する速度で進み、かつて「知的労働」の牙城であったホワイトカラーの足元を根底から揺さぶっている。
この未曾有の変革期に、誰よりも冷静に、そして鋭く未来を見据える人物がいる。セブンセンス税理士法人の大野修平氏。公認会計士・税理士として業界の最前線に立ちながら、AIがもたらす未来についてSNSや講演を通じて、AI活用の未来を伝えたり、時には警鐘を鳴らすなど、新たな時代の羅針盤を示し続けるトップランナーだ。
今回、以前から大野氏への憧れを公言していたDFE代表の向井隆昭が、その思考の深淵に迫る。AIの登場で士業、ひいてはDFEを含むホワイトカラー全体の仕事はどう変わるのか?私たちはこの時代をどう生き抜くべきか?これは、未来への警鐘であり、同時に希望のメッセージでもある。
大野 修平(おおの しゅうへい)
セブンセンス税理士法人 / 公認会計士・税理士 / ディレクター
会計業界におけるAI活用の第一人者。2022年のChatGPT-3.5登場直後から、そのポテンシャルとリスクをいち早く察知し、業界の変革を提唱。SNSでの情報発信のほか、全国の税理士事務所向けに「AI活用研究会」(ページ下部にリンク設置あり)にて講師を務めるなど、テクノロジーと会計の未来を繋ぐための活動を精力的に行っている。
向井 隆昭(むかい たかあき)
株式会社データ・ファー・イースト社 代表取締役
企業のバックオフィス支援やコンサルティングを手掛けるDFEの代表取締役。テクノロジーがもたらす未来や新しい働き方について興味津々。
向井:先生、今日はお忙しい中ありがとうございます!早速ですが、先生がAI、特に生成AIに注目し始めたのは、やはりChatGPTの登場がきっかけだったんでしょうか?
大野:こんにちは!ええ、そうです。ChatGPTの3.5が出た時ですね。触った瞬間に「あ、これは社会を変えるテクノロジーだぞ」と、ドキドキワクワクして。それがきっかけです。

向井:当時はまだ「おもちゃみたいだ」という声も多かったですよね。僕も目の前の仕事から逃げるように、見ないようにしていました(笑)。
大野:みんなそうだと思いますよ。僕は当時、結構騒いだんですよ。「これはやばいよ」「僕らの仕事の7〜8割が奪われる可能性があるよ」みたいな話をしてたんですけど、ほとんど相手にされなかったですね。
向井:なぜだったんでしょう?
大野:我々の業界って、そこに至るまでに「クラウド会計」とか「RPA」とか、色々あったんです。「クラウド会計で人間が入力しなくて良くなる」「RPAで単純業務はなくなる」みたいな触れ込みがあったけど、結局社会は変わらなかったよね、と。みんな、そういう経験をしていた。
向井:「どうせ今回も同じだろう」という空気感があったわけですね。
大野:そうなんです。でも、僕はRPAの時は全く動じなかった。「こんなものはExcelのマクロに毛が生えたくらいのもんだし、こんなもので奪われるような仕事じゃない」と思っていました。でも、生成AIは明らかに違った。僕たちの仕事を「肩代わりできるだろうな」と感じました。
向井:その後、GPT-4が登場します。
大野:そう、2023年の3月15日。GPT-4は僕の中で3.5を超える衝撃でした。でも、この日って僕らの業界にとっては確定申告の最終日で、1年で一番忙しい日なんです(笑)。だから、やっぱり誰も反応しなかった。「こんなおもちゃみたいなやつの新しいのが出たからって、手を止めるもんじゃない」と。
向井:業界が一年で最もAIを触る暇がない日だったんですね(笑)。
大野:幸い、僕は税務をほとんどやっていなかったので、早速触ってみて、3.5からガラッと変わっていることに気づきました。「あ、なんかすごいスピードでこっちに迫ってきてるな」と。ハルシネーション(もっともらしい嘘をつく現象)もだいぶ抑えられていた。それで最初に連絡したのが、領収書スキャンサービスの「STREAMED(ストリームド)」の創業者、菅藤さん。彼もすごく危機感を感じていて、「これは世界を変えますね」という話になりました。
- 菅藤達也- Effic https://x.com/tatsuyakanto
向井:先生はXで「これまでは考えることに価値があったけど、これからは人間は実行に集中するべき」とポストされていて、非常に衝撃を受けました。
大野:まさにそこが核心だと思っています。人類って、歴史上ずっと「考える」ことが地球上で一番得意だったわけじゃないですか。他のことは他の存在に任せて、僕らは「考える」ことに特化してきた。パスカルが言ったように、僕らは「考える葦」だったんです。

向井:考えるチャンピオンだった、と。
大野:そう。でも、つい数ヶ月前、そのチャンピオンの座を明け渡すことになった。今年の4月に出たChatGPT-o3はIQが132と言われ、大半の人類より賢い。そして先日出たGPT-5はさらに賢い。僕たちの知能を凌駕する存在が、今や誰のスマートフォンの中にでもいるんです。うちの小学4年生のチビも、今年の夏休みの自由研究はChatGPTと一緒にやってましたよ(笑)。
向井:すごくいい使い方ですよね!小学生にはGoogle検索って難しい。どう検索していいかわからないし、検索結果の漢字は読めないし、どのサイトが正しいかも選べない。でもChatGPTなら、相手が小学4年生だと分かった上で、ちゃんとその子に合わせた言葉で説明してくれる。確かに。大人相手でも同じことが言えますね。
大野:そうなんです。IQ130以上の頭脳が、僕らIQ100の人間に合わせて「お前らにはこれぐらい丁寧に説明しないとわかんないだろうから」って、分かりやすく歩み寄ってくれる。このスマートフォンの中の超頭脳を、使わないのはもはや悪であり、エゴであり、自己満足でしかない。
向-井:「考える」という行為自体が、自己満足になる…。強烈な言葉です。
大野:悲しいですよ、僕だって。人類が何万年もかけて築いてきた「地球上で最も賢い存在」という地位を、まさか2025年になって手放さないといけないなんて。にわかには信じたくない。でも、現実はもうそうなってるんです。じゃあ、人間って不要なのか?いや、何か役割を担えるはずだ。それが「実行」だと僕は思うんです。
向井:AIの進化をここまで見据えている先生が、どうやって大手税理士法人でメンタルを保ちながら仕事をしているのか、すごく気になります。
大野:(笑)。まあ、なんとかなりますよ。今までもそうやって来たから。会計士試験だって、やる前はすごく難しいと思うけど、やってみたらできた、という人が何万人もいるわけですから。やったことなくても、やってみたら意外とできちゃうんです。

向井:その「やってみる」精神が、先生のキャリア相談にも表れていますよね。会計士の方から「どのキャリアがいいですか?」と聞かれることが多いとか。
大野:よく聞かれますね。監査法人で頑張るのもいいし、スタートアップに行くのも、独立するのもいい。選択肢がたくさんある中で「何がいいですかね?」って。でも、そんなの何でもいいんですよね。正解なんてないんですから。
向井:何でもいい、ですか。
大野:人生って残酷なので、成功が約束されていることなんて全くない。でも、自分が選んだものを成功にしていくことはできると思うんです。自分の人生だから。であれば、最後の土壇場で踏ん張りが効く、「本当に自分がやりたいな」と思ってることをやるのが一番いい。やりたくないことを打算で選んでも、究極のところで頑張れないですよ。
向井:成功する前にやめるから、失敗する、ということですね。
大野:そうそう。AIの話もこれと繋がります。AIに相談すれば、成功確率の高い選択肢を5個くらい出してくれる。失敗確率は減らせます。その中から「俺って何がやりたいんだっけ?」と考えて選び取る。あとは、日々それをやるだけ。
向井:そこで「実行力」が問われるわけですね。
大野:その通りです。今までは「考える」ことが重要視されていたから、結果が出なくても「でも頑張って考えてくれてたから」と評価された部分があった。でも、もう言い訳ができなくなる。企画を立てた後の、人を巻き込む力、推進していく力、進捗管理する力…そういう泥臭い部分でしか評価されなくなったってことです。本当は、仕事って元々そういうもんだったんですけどね。
向井:ここまでのお話、本当に深く整理されていて驚くばかりなんですが、その思考って、普段からAIと壁打ちして磨いているんですか?
大野:いや、これは自問自答ですね。
向井:えっ!?「考えるのは悪だ」と言いながら、そこはAIを使わないんですか!?
大野:あはは、面白いですよね。やっぱり、抗ってるんじゃないですか。人間の悪いところですね(笑)。
向井:いやいやいや(笑)。でも、なぜです?
大野:僕は、仕事と人生は切り分けて考えるべきだと思ってるんです。仕事は、論理的で合理的であるべき。なるべく失敗せず、成功確率の高いところにリソースを投下してゴールを目指す。だから、それが得意なAIを徹底的に使うべきです。
向井:一方で、人生は?
大野:人生は、非合理的でいい。自己満足の世界ですから。寄り道が多い方が絶対に面白い。いっぱい無駄なことをして、「あ、間違っちゃったな」とか「これ違ったか」とか、たくさん失敗していいと思うんです。
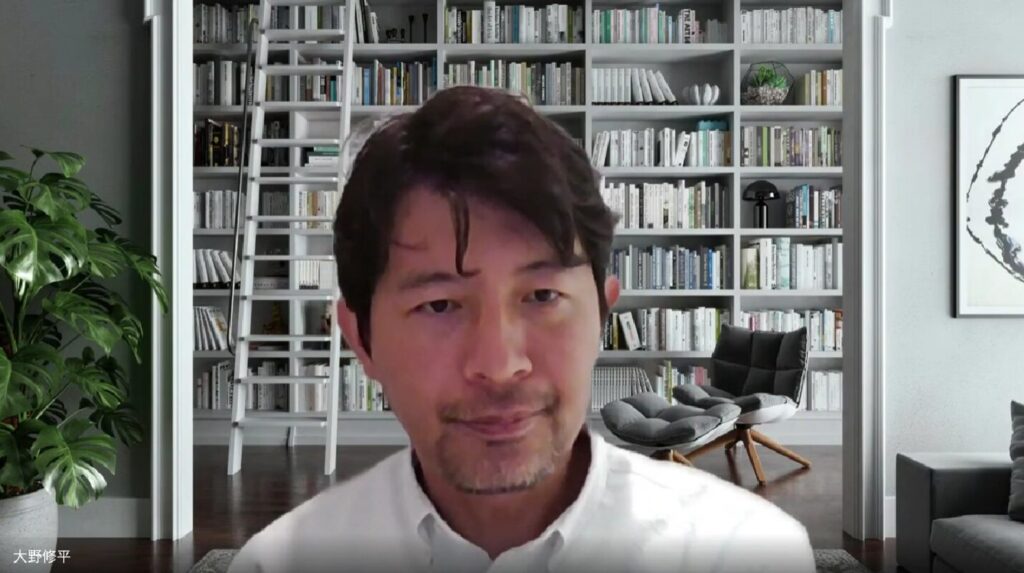
向井:寄り道が多い方がいい。
大野:そう。食事とかまさにそうじゃないですか。栄養素だけサプリで摂るのが合理的かもしれないけど、それって豊かさっていう観点から見ると物足りない。まずいものを食べる経験って絶対面白いし、ネタになるし、まずいものを知るからこそ、うまいものがわかる。それも豊かさだから。人生ってそういうものだと思うんです。だから、自分の人生の問いについては、AIとの壁打ちでは無理。全部自分で経験して、自分だけのストーリーを作っていけばいいんです。
向井:最後に、もう少し具体的な未来予測を。先生の事務所では、仕訳のような業務にもAIを活用されているとのことですが、そうなると既存の会計ソフトの未来も変わってきますよね。
大野:変わるというか、なくなるかもしれないですね。
向井:なくなる、ですか。
大野:僕は、2年後くらいには、Googleドライブに必要な資料をバカバカ放り込んでおけば、AIが勝手に読み取って「試算表作って」と言ったら試算表がババっと出来上がる、そういう世界が来ると思っています。
向井:2年後!10年とか20年後ではなく。まぁ確かに弊社でも開発していて、正確性の担保のために念のため仕訳機能をクラウドを活用していますが、自社のGoogle Cloud Platformを活用してAIで完了まで持ち込めると見てデバックしていってます。
大野:そうですよね。ChatGPT3.5というおもちゃみたいなものが出てから、まだ3年も経っていない。このスピード感を考えれば、もっとすぐ来るでしょうね。

向井:ということは、最近黒字化したSaaS企業も…。
大野:厳しいでしょうね。いくらSaaSにGPTを組み込みましたと言っても、それはほんの1〜2年の話。いずれ「生」のGPTに「試算表作って」と言えばできるようになる。そうなると、いわゆる「SaaS is dead」です。本家である巨大AIの性能に依存しているサービスは、本家がアップデートされれば不要になる。賢い人はもうSaaSで起業はしないでしょうね。
向井:では、これからの社会はどうなるんでしょう。ホワイトカラーの大量失業で、格差が広がるんでしょうか。
大野:いや、僕はプレイヤーの入れ替わりが起こると思っています。今までホワイトカラーだったけど実行力がない人たちは、市場にいらなくなるかもしれない。一方で、今はブルーカラーの現場にいるけど、決められたことを実行するのがすごく得意な人たちの社会的地位や待遇は、間違いなく上がっていく。
向井:ルールが変われば、活躍する選手も変わる、と。
大野:そうです。社会全体で見れば、僕はますます活性化していくと思いますよ。これまで「考える」というプロセスに、ものすごい時間とコストがかかり、停滞していたことがたくさんあった。それをAIに渡しちゃえば、あとは人間が選択肢の中から選び取って「じゃあ、これやるぞ!」でみんなで動き出せる。停滞がなくなる分、社会は活性化するんじゃないでしょうか。
向井:なるほど…。失業時代というより、人間の役割が再定義される時代なんですね。なんだか、悲観していた未来が、少し明るく見えてきました。
大野:そう、なんとかなりますよ。今までだって、なんだかんだで僕ら、なんとかなってきたじゃないですか(笑)。
向井:確かに!先生、今日は本当に刺激的なお話をありがとうございました。
「考えるのをやめる」—大野先生の言葉は、知的労働にプライドを持ってきた我々にとって、耳が痛く、寂しさすら感じさせるかもしれない。しかし、それは思考停止を推奨するものでは決してない。AIという新たな相棒を得た人類が、次のステージへ進むための「役割分担」の提案でしたね。
仕事は合理的に、AIを使い倒して結果を出す。人生は非合理的に、寄り道と失敗を楽しみ、自分だけの物語を紡ぐ。
その切り分けこそが、AI時代の荒波を乗りこなし、人間らしく豊かに生きるための鍵なのかもしれない。大野氏の言葉は、先行きの見えない時代を生きる私たちに、力強い覚悟と希望を与えてくれたような気がしました。
DFE向井
今回の対談には、編集者としてリモートで立ち会わせていただいた。画面越しにも伝わってきたのは、大野修平氏という人物の圧倒的な「解像度」である。多くのビジネスパーソンがAIに対して抱く漠然とした期待や不安を、彼は驚くほどシャープな言葉で次々と定義していく。
「考えることは悪になる」「仕事は合理的、人生は非合理的」「ブルーカラー的ホワイトカラー」—。
一つひとつが鋭く、刺激的でありながら、その根底には一貫して、人間という存在への温かい眼差しと楽観主義が流れている。インタビュアーの向井氏との気心知れたやり取りの中で、大野氏が時折見せる少年のような笑顔は、彼が語る「なんとかなる」という言葉に、不思議な説得力を与えていた。
AIがもたらすのは、人間の仕事の終わりではない。むしろ、人間が「人間らしい仕事」に回帰するための、壮大な役割分担の始まりなのかもしれない。この記事が、読者の皆様にとって、変化を恐れるのではなく、未来を「実行」していくための一助となることを願ってやまない。
対談の要点を、忙しいビジネスパーソンのためにQ&A形式で端的にまとめました。
A1. 「なくなる」というより「根本的に変わります」。これまで価値の源泉だった「考える」仕事(調査、分析、資料作成など)はAIに代替されます。人間に残るのは、AIが出した選択肢から最善のものを選び取り、顧客と対話し、プロジェクトを推進する「実行」の役割です。価値は「思考」から「行動」へ完全にシフトします。
A2. 「実行力」です。AIが立てた完璧な計画を、実際に手を動かし、人を巻き込み、泥臭く形にしていく能力が全てになります。大野氏はこれを「ブルーカラー的ホワイトカラー」と表現しました。考えるだけの評論家は不要になり、行動するプレイヤーだけが評価される時代が来ます。
A3. 「仕事」と「人生」を明確に切り分けることです。
- 仕事では、徹底的に「合理的」になりましょう。AIを相棒としてフル活用し、最短距離で結果を出すことに集中します。
- 人生では、むしろ「非合理的」になりましょう。寄り道や失敗を楽しみ、自分だけの経験を積むことが人間的な豊かさに繋がります。「なんとかなる」という楽観的な姿勢が重要です。
A4. 非常に厳しい未来が予測されます。大野氏は「SaaS is dead」と断言しました。いずれGoogleドライブなどに資料を入れるだけでAIが直接財務諸表を作成できるようになると、多くの中間的なSaaSは存在意義を失います。本家である巨大AIに機能を飲み込まれる可能性が高いと考えておくべきです。
A5. いいえ、大野氏は楽観的です。大量失業の時代が来るのではなく、社会の「プレイヤー交代」が起こると見ています。「実行力」のある人が新たな主役となり、これまで停滞の原因だった「考えるコスト」が劇的に下がることで、社会全体はむしろ活性化していくと予測しています。
- セブンセンス税理士法人 https://seventh-sense.co.jp/
- AI活用研究会 https://www.ai-kenkyukai.com/
- 大野先生のXアカウント https://x.com/Shuhei_Ohno
- 株式会社データ・ファー・イースト社 https://dfe.jp/
- DFEのXアカウント https://x.com/datafareastco