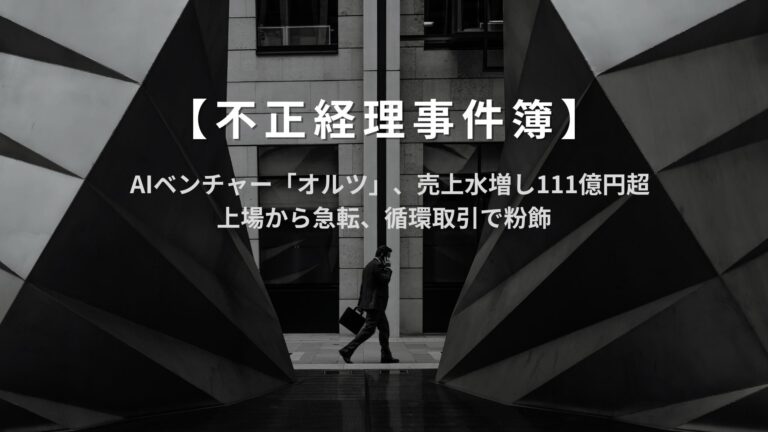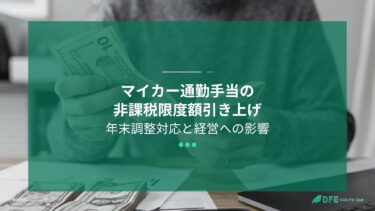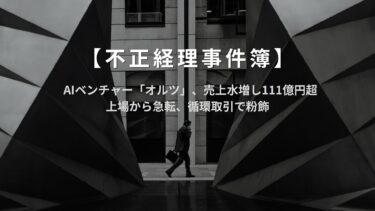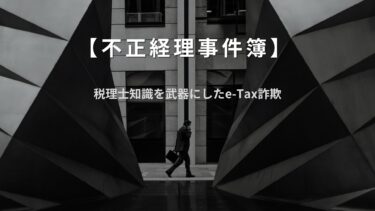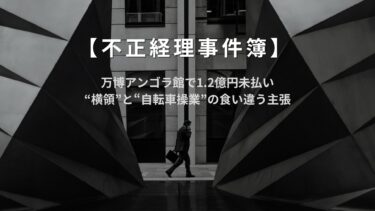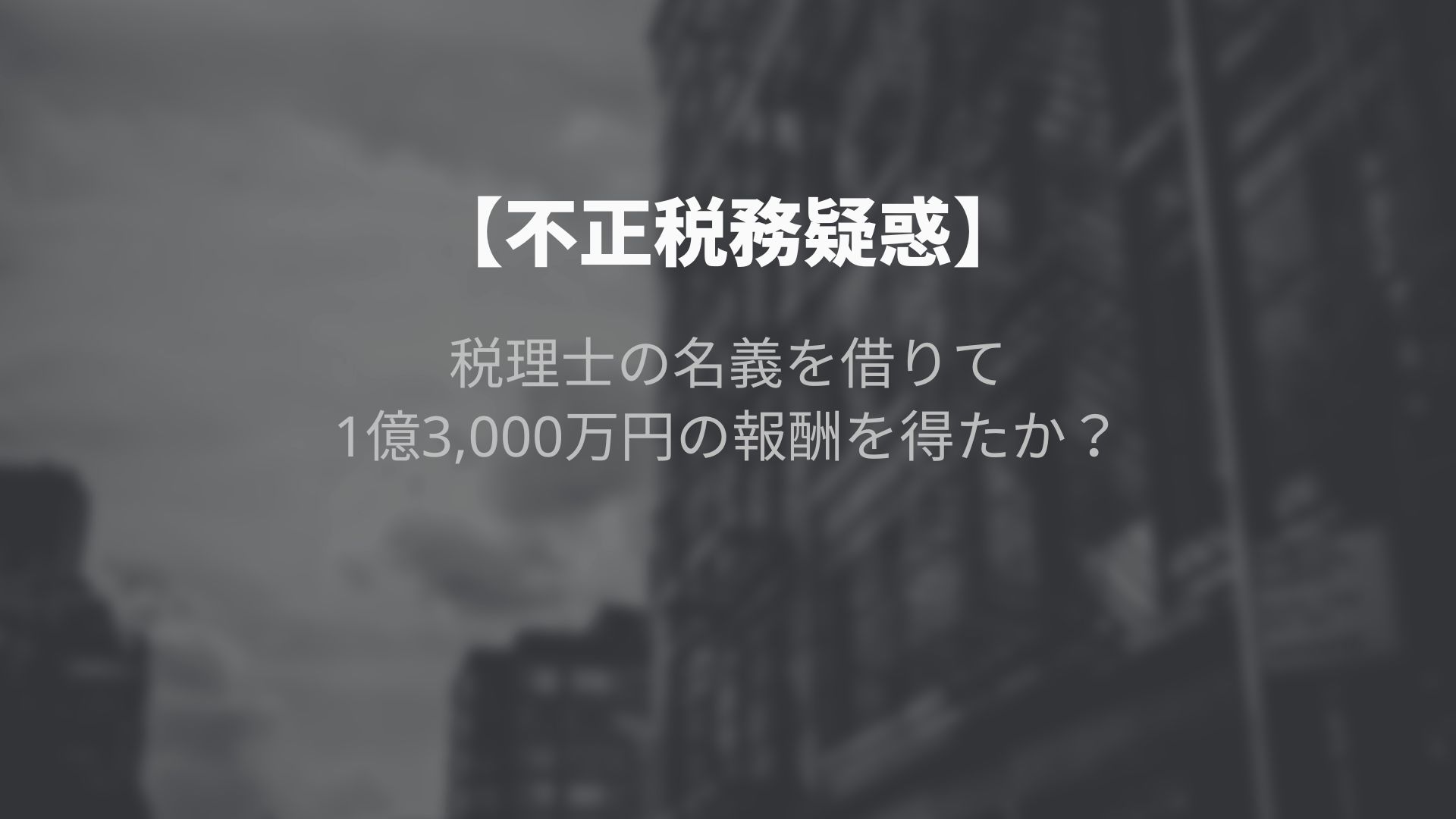AI議事録サービスで注目を集めたベンチャー企業「オルツ」。
しかし急拡大の裏には、売上高を約111億円にのぼる数値で水増しした粉飾決算が隠されていました。
旧経営陣4人が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)容疑で逮捕された今回の事件。
上場・再生手続き・サービス停止へと至った経緯を整理し、これからの経理・監査体制に向けた教訓として押さえたいポイントも紹介します。
事件の経緯
オルツは、2022年12月期から2024年12月期にかけて、実際の売上を大きく上回る金額を開示していました。
水増し額は、総額約111億円にのぼり、開示した売上の8割超が虚偽だったとみられています。
旧経営陣4名(元社長・前社長・営業部門長・経理部門長)は共謀のうえ、関東財務局に虚偽の有価証券届出書を提出。さらに上場後も、有価証券報告書に偽りの数値を記載していた疑いが持たれています。
粉飾の手口として判明したのは「循環取引」。
広告代理店や研究開発委託先など複数の関係企業に資金を支出し、その資金を別ルートで自社へ戻すことで、実態のない売上を計上していました。
手口と数値の詳細
2022〜24年6月期:実際売上 約11億3,000万円 → 虚偽記載 約96億2,000万円
2024年12月期:実際売上 約10億9,000万円 → 虚偽記載 約60億5,700万円
架空支出:広告宣伝費 約138億円、研究開発費 約16億円
架空アカウント:有料アカウント2万8,699件のうち8割超が実態なし
捜査は東京地検特捜部と証券取引等監視委員会が連携して進められました。
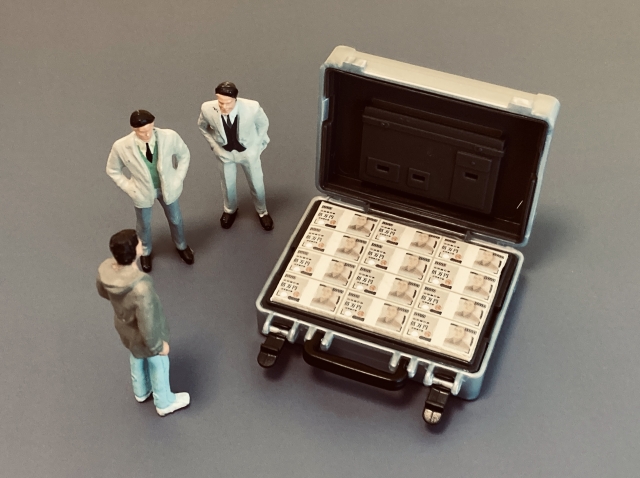
なぜ起きたのか
この不正は、急成長を期待されたAIベンチャー特有の「成果への過度なプレッシャー」が背景にありました。
市場からの期待に応えようとするあまり、経営陣は上場を急ぎ、業績を実際よりも良く見せかけることで資金調達を有利に進めようとしたとみられています。
一方で、社内のガバナンス体制は十分に整っておらず、内部統制や監査の仕組みが機能していませんでした。監査法人や主幹事証券会社に対しても、十分な説明責任を果たしていなかったとされます。
また、実際の売上実態や取引先の確認が不十分であったことが、循環取引や架空計上の発見を大幅に遅らせる結果に。企業としての透明性や内部統制の欠如が、今回の大規模な粉飾を長期化させた最大の要因といえます。
教訓と再発防止策
今回の事件は、「数字合わせ」ではなく、実態に基づく経営管理の重要性を改めて浮き彫りにしました。
まず、売上計上には、実際にモノやサービスが提供されたことを証明できる記録を徹底する必要があります。循環取引の監視も強化し、実績のない取引先や異常な売上増加には、内部監査部門・外部監査人が連携して注視する体制が求められます。
また、監査法人の独立性を確保し、監査範囲や証拠記録を充実させることで、会計情報の透明性を担保することが不可欠です。経営陣のガバナンス強化も欠かせず、経理部門が「数字作り」に走らないよう、取締役会や監査役会によるチェック機能を明確化することが重要です。
さらに、スタートアップこそ“実務の裏付け”を重視すべきです。成長志向に偏らず、開示の適正化こそが企業価値を支える土台となります。
そして、こうしたガバナンス強化や実務体制の整備には、第三者による専門的な支援を取り入れることも有効です。
われわれDFEのような経理・会計業務のアウトソーシングサービスを活用すれば、客観的な視点でのチェックや、内部統制の仕組みづくりを支援してもらうことができます。外部の専門家と連携し、透明性の高い経営基盤を築くことこそ、再発防止への確かな一歩といえるでしょう。
まとめ
A. 2022年12月期〜2024年12月期の売上高のうち、約111億円が水増しされ、実際の売上の8割超が虚偽
A. 広告代理店や研究開発委託先を介した循環取引により、架空の売上を自社に計上していた
A. 売上計上の実態確認、循環取引監視、監査法人の独立性確保、経営陣のガバナンス強化、外部専門家やアウトソーシングサービスの活用
スタートアップは挑戦が重要ですが、企業の信頼を守ることが最優先。
オルツ事件は、AIベンチャーが急成長のプレッシャーや上場のインセンティブで売上を水増しした典型例です。
循環取引で業績を偽装した手口は、内部統制や監査の重要性を改めて示しました。
スタートアップほど外部専門家の活用が企業価値を守る鍵となります。
バックオフィス業務のアウトソーシングは、DFEにお任せください。