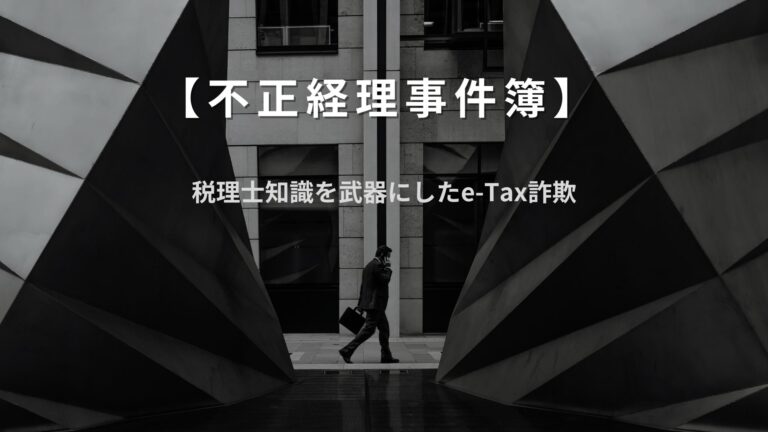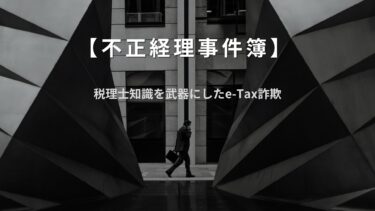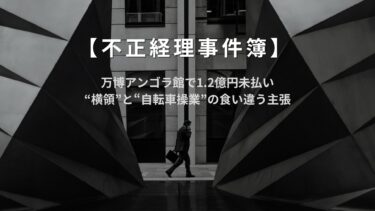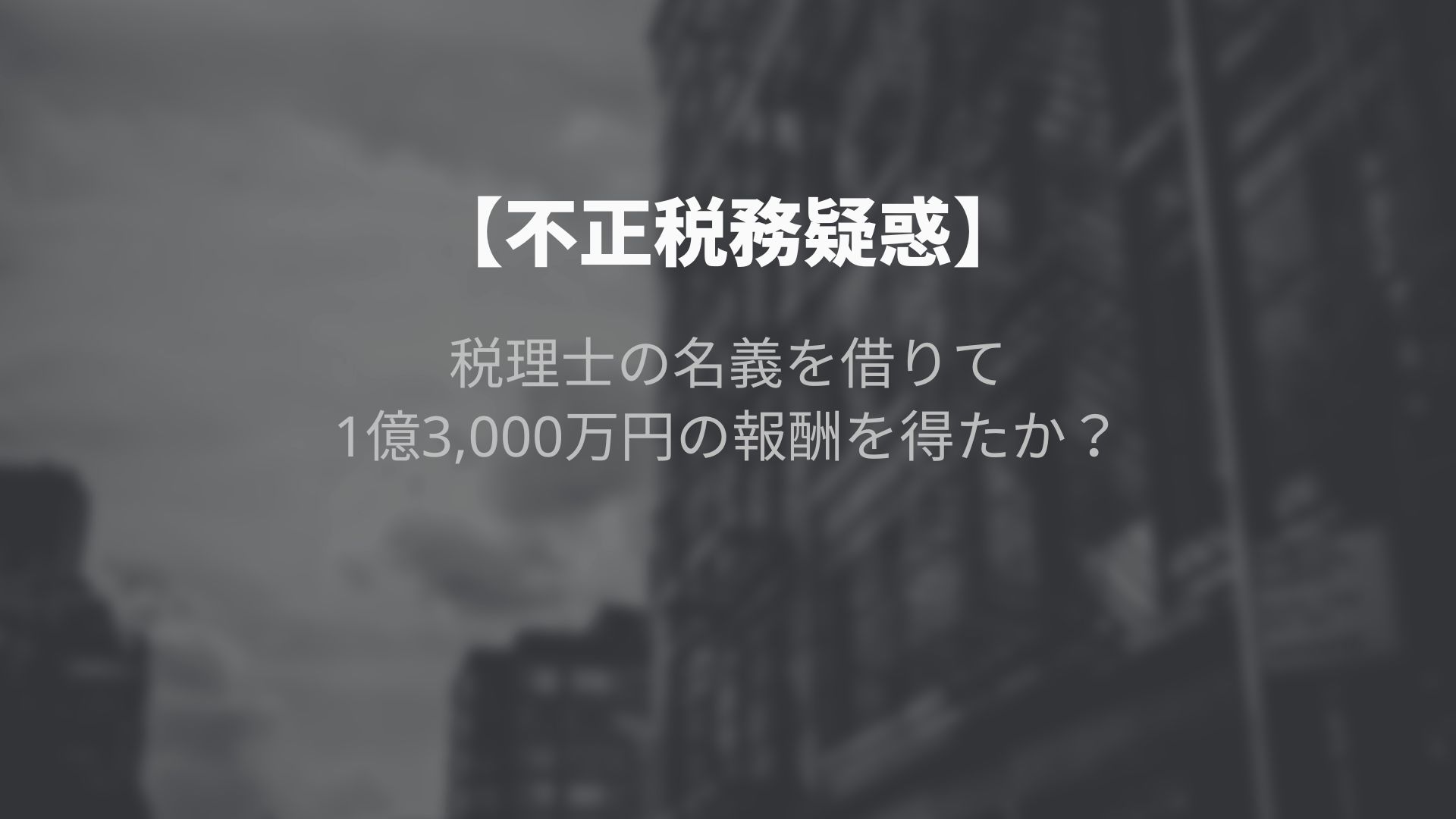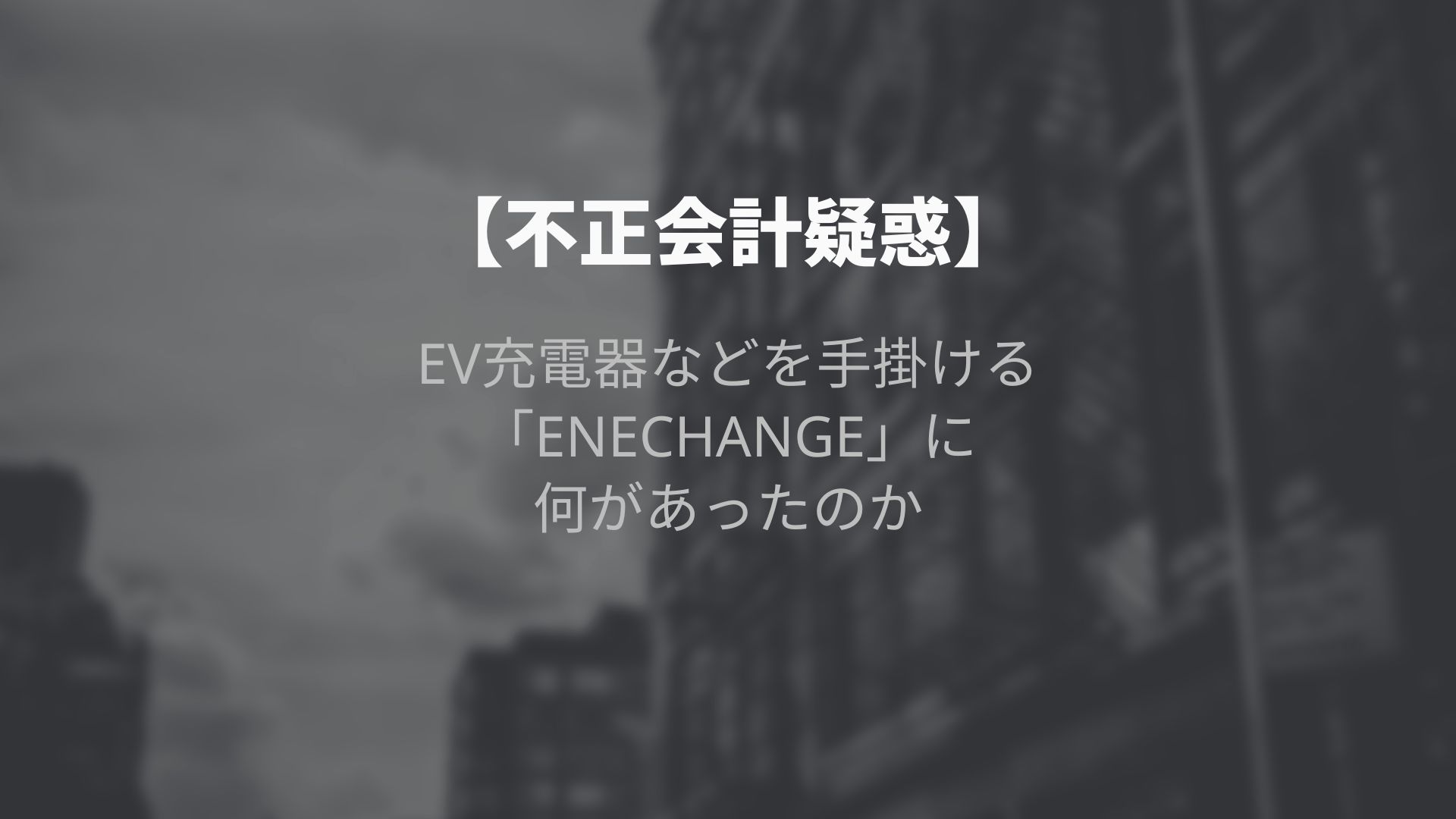国税庁が提供する電子申告・納税システム「e-Tax」を悪用し、全国の税務署から還付金をだまし取った詐欺事件で、主犯格の男の初公判が開かれました。
税務の専門知識が犯罪に転用されるという、近年の不正の新たな手口を示す事件です。
元税理士事務所勤務経験者による不正の手口
詐欺罪に問われているのは、東京都でデザイン業を営む小笠原惇被告(40)。
2024年7月から9月にかけて、北海道・愛媛・宮崎の各税務署に虚偽の所得税申告書を提出し、総額608万円の還付金を不正に受け取ったとされています。
小笠原被告は他人のIDとパスワードを不正に入手してなりすまし、実際には存在しない事業収入や経費を申告していました。
検察によれば、被告は大学を中退後、税理士事務所に勤務しており、その際に得た税務知識を詐欺に悪用したとみられます。
小笠原被告は前科があり、2024年4月に刑期を終えて出所した直後から犯行を計画していたとされています。
秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」を通じて接点を持ったのは、サイバー犯罪グループ「荒らし共栄圏」のリーダーを名乗る17歳の少年でした。少年らと連携した小笠原被告は、詐取した還付金の一部をビットコインなどの暗号資産に換金し、資金の追跡を困難にしていました。
匿名性の高い通信手段と暗号資産の組み合わせは、近年の不正資金隠匿の常套手段となっており、捜査当局も警戒を強めています。

流出したIDとパスワード
検察側は、SNS上でやり取りされたとみられる300件以上のIDとパスワードの記録を証拠として提出しています。
これらは、なりすまし申告に用いられた可能性が高く、背後に大規模な情報流出ルートが存在することを示唆。流出原因は、過去のデータ漏洩や管理の不備、SNSやメールでの情報のやり取りが狙われたことなどが考えられます。
小笠原被告は起訴内容をおおむね認めていますが、弁護側は「証拠の一部が開示されていない」として、一部の認否を留保しました。今後の審理では、証拠開示をめぐる攻防が焦点となる見通しです。
e-Taxの盲点
この事件が注目されるのは、e-Taxという正規の行政システムが犯罪の温床となった点にあります。
ID・パスワードによる本人確認が行われているにもかかわらず、なりすましによる虚偽申告が可能だったことは、制度上の脆弱性を浮き彫りになりました。
また、税務申告に精通した人物が内部知識を利用し、不正を「本物らしく」装うことで、発覚までの時間を稼いでいたとみられます。専門性とデジタル技術、匿名性の高い通信・資金移動手段が組み合わさることで、不正のハードルは大きく下がりつつあるのが現状です。
今後の課題
今後の裁判では、共犯関係の詳細や、他の関係者への波及が明らかになる可能性があります。既に300件を超える個人情報が流出していることから、被害の範囲は608万円にとどまらない可能性もあります。
国税庁や税務署には、なりすまし対策の強化が急務です。二段階認証の導入や、申告内容の異常検知システムの精度向上、ID管理の徹底など、制度面の見直しが求められます。また、専門知識を持つ人材による不正の抑止という観点からも、税理士事務所などの内部統制強化が必要になるでしょう。
まとめ
Q1:企業としてどのようにID管理を強化すべきか?
A1:二段階認証の導入やパスワードの定期変更、アクセス権限の厳格管理など、基本的な内部統制を徹底すること
Q2:元社員や経理担当者による内部不正はどう防ぐ?
A2:退職時のアクセス権解除や、経理データの閲覧・操作ログの記録、重要情報の持ち出し防止策を整備すること
Q3:起業家や中小企業が特に注意すべき点は?
A3:e-Taxやクラウド会計などデジタルシステムの利用にあたり、ID・パスワード管理だけでなく、入力内容の二重チェックや異常検知の仕組みを導入すること
e-Tax詐欺事件は、専門知識とサイバー技術が結びついた新たなタイプの税務犯罪として大きな警鐘を鳴らしています。正規の仕組みであっても、使い方次第で不正の温床となり得るのです。
また、税務知識を持つ元社員や経理担当者が内部情報を持ち出し、不正に加担する事例も増えています。「自社には関係ない」と考えず、あらゆる角度から備えることが重要です。
DFEは、こうした不正リスクへの対応を多面的にサポートいたします。